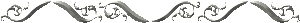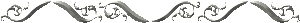ぼーだら 作
1930年5月 パリ
初夏のパリは美しい。だが、目を閉じるとあの街の5月が浮かぶ。やはり美しさで知られた街の、あの一番醜い夏。
シテ島の南、カルティエ・ラタン。非の打ちどころのないノックの後、彼はほうっと詰めていた息を吐き出した。
今の彼は、決して豊かではないにしろそれなりの信用のある勤め人だ。優美なマンサール屋根にも、弁護士の呼び出
しにも動じる必要はない筈だ。
てきぱきした物腰の若い男が顔を出した。
「アレクサンドル・ユスティノフです。トマ・ファブリ弁護士はご在宅ですか?」
「突然お呼び立てして失礼いたしました、ムッシュー・ユスティノフ」
「アメリカから問い合わせがあったと聞きましたが」「直截な方ですね」
「私はビジネスマンです」「それなら話は早い」弁護士は音を立てて書類を取り出した。
「……座ってもいいですか?」「これは失礼しました」声音の割に、仕草はぞんざいである。
「ニューヨークの、フェントン&サンズ事務所はご存知で?」「いいえ」
「では、ヴァン・トリップ家は?」「聞いたこともありません」
「今回の依頼人です。ミス・ベアトリス・ヴァン・トリップ。先代のコーネリアス氏の令嬢ですよ。彼女がフェントン
&サンズに依頼して、ディック・フェントン……顔の広い男でしてね……がベルリンのオステン=ザッケン男爵に問い
合わせロシアの亡命者たちに聞いて回ってもらって、なんとかあなたにたどり着いたわけです。私はフェントンに指名
されてミス・ベアトリスの代理人を務めていましてね。焦れてますよ、彼女」
「ご用件が分かりかねますが。そのミス・ベアトリスが私に何の用なのですか?」
「ミス・ベアトリスは、弟ウィリアム氏の妻ミセス・サンドラ・ヴァン・トリップと争っていたんですよ。サンドラが
弟の財産を不当に処分したと言ってね。彼女の旧姓はウスチノフ、ミス・アレクサンドラ・ウスチノフです」
……サンドラ。彼女はそう名乗っているのですか? なんだか別のひとみたいだ。ロシアではシューラと呼ばれてい
ました。ええ、私の従妹です。父親を亡くした私を、彼女の父、私には伯父にあたるセミョンがペテルスブルクに呼ん
だんです。ヴィテブスク駅に着いた時、伯父と一緒にいたのが彼女でした。可愛らしい子供でしたよ。白い毛皮のフー
ドからさらさらの金髪ときらきらした青い目がのぞいていましてね。
「よく来たな。これが娘のサーシャだ」え、と思いましたよ。だって、私もサーシャと呼ばれていたんですから。恐る
おそるそういうと、伯父はちょっと眉を下げるようにしました。伯父はムジーク(農民)顔というか、朴訥らしい人が
よさそうな感じの顔立ちなんでしたが、結構怒りっぽいうえに根に持つたちでしてね。そんなふうに眉を下げるのは相
当に気分を害したしるしです。まあ後で分かったことなんですけれど。
「お前の方は、サーシカじゃだめなのか?」でも、ロシア語で「サーシカ」は「サーシャ」に比べるとちょっと相手を
軽んじた感じなんです、子供か召使を呼ぶような。やっぱり嫌でした。そこでいきなり彼女が口をはさんだんです。
「パパ! 早く行かないとマダム・ヴィルロワのルソンが始まってしまうわ!」
……ええ、彼女をピアノのレッスンに送る途中だったと後で聞きました。
「その子がサーシャでいいじゃないの。あたしの方が変えたらいいのよ」彼女は愛らしく顎を持ち上げました。
「あたしのことはシューラと呼んで頂戴」
思えば、彼女自身がありふれたサーシャという呼び名が面白くなくて、もっと洒落たものに変える機会を窺ってたん
でしょうね。でも私の方は嬉しかった。なんというか、自分が「つながった」気がしたんです。伯父の家での生活は、
故郷とは何から何まで違っていて、今こんなことをいうのもなんですが、ちょっと「落ちぶれた」感じがしました。伯
父は手広く商売をしていましたから、ヴァシーリィ島の瀟洒な邸宅は最新流行の品で溢れ、田舎育ちの身には外国にも
思えたくらいだった。都会人の物腰もよそよそしく感じられたし、一方で自分がいかにも土臭く下品な気もした。伯父
一家もそんな私を持て余していたんでしょうね。一家の花形は何と言ってもシューラだった。美人で賢く、伯父として
は玉の輿に乗せる気満々、例のマダム・ヴィルロワのレッスンも、貴族の娘たちと知り合わせるためだったらしい。本
当に上流の令嬢方は、自宅に教師を呼びつけるものだと知って止めさせましたが。伯父は、ほとんど娘を崇拝していた
といっていいくらいでした、成り上がり臭の抜けない自分に比べて、娘の上品な愛らしさがかけがえのないものに思え
たんだと思います。私は伯父の会社が学校のようなものでしたが、彼女には金に糸目を付けず外国人の家庭教師を付け
ていた。実際、シューラはめきめきと美しくなり、伯父の目には……ええ、そうです、言ってしまえば私の目にも……
皇帝の姫君にだって見劣りしない、お伽噺のお姫様に見えていました。
伯父は野心家でした。そして……もうこの話も時効なんでしょうね……政治にも関心を持っていました。若い方に説
明するのは正直難しい。1905年、あの頃ロシアには沸き立つような政治の季節があったのです。軍隊が国民に銃を向け
皇帝の威信が地に落ち、暗殺、反乱、ストライキに次ぐストライキ、まともな経済活動も政治活動もできなくなってい
たのに、これからくる時代は確かによいものだと何故か皆が信じていた。私も伯父の会社で伝票に埋もれながら、事務
員同士で地下出版の新聞を回し読みしたりしてましたよ。無論伯父は、そこまで過激な人間ではありません。労働運動
なんてとんでもない、ただもう少し商売がやりやすくなるとありがたい、という程度。それより彼は、成り上がりらし
い上昇志向で貴族や名家の政治独占に反発し、自分こそが政権に入るべきだと考えていた。そんな時期、ウスチノフ家
に現れたのがアルラウネ・フォン・エーゲルノフだったのです。
一目見たら忘れられない、ごく稀にそんな人間がいるものです。アルラウネがそうでした。華麗な美貌、優雅な挙措
と火を吐くような熱弁、あの時代の婦人ながらはっきりと感じ取れる知性、そんな言葉を連ねても彼女の持っていた強
い強い磁力のようなものは表せますまい。ペテルスブルク大学の教授の娘でした。まだ10代のころに革命運動に参加し
た恋人が処刑され、自分も亡命したと聞きました。ええ、職業革命家、そう呼んでもいい。野心だけは売りに出せそう
なくらいあっても、政治に伝手のない伯父が夢を託したのが彼女だった。あの颯爽とした華やかさ、そこに立っている
だけで白い光が溢れてくるような佇まい、アルラウネというひとには他人が夢を託したくなるような魅力があった。圧
倒されていましたよ、伯父よりむしろ私が……そしてシューラが。父親の方針で学校には行かず専ら家庭教師について
勉強していたシューラにとって、皇帝や政府と切り結んで生きてきた美しいアルラウネの出現は、外の世界が嵐のよう
な勢いで吹き込んできたようなものでした。シューラはアルラウネを崇拝していた、と思います。彼女の帽子の羽根飾
りまで輝いて見えていたことでしょう。アルラウネにかかわるものすべてが素晴らしく見えていた……最初はきっとそ
れだけのことだったと思うのです。
アルラウネには弟がいた……正確には処刑された彼女の恋人の弟でした。アレクセイという名の私と同じくらいの年
ごろの若者で、さぁ私などには不満顔の若造にしか思えなかった。アルラウネが伯父のような実業家に近づいては軍資
金をかき集めたり指示を与えたりするのを、何やら不機嫌な目で見つめていて、ときどきどこへともなくふいっと姿を
消す。容姿はいい方でした。背が高くてきりりとした顔立ちをしていて、屋敷の女中たちには騒がれていましたね。姫
様育ちであまり他人に関心を持たないシューラが、彼の名前を知っていたこと自体、私には驚きでした。アルラウネの
弟だったから、女中が騒いでいたから興味をひかれた。それが、すべての始まりだったのでしょうか? あのシューラ
も所詮恋に恋するひとりの乙女だったのでしょうか……。
伯父がアレクセイにシューラとの結婚を持ちかけて断られたということを、私は伯父の口から聞きました。掌中の珠
の愛娘の結婚相手にしては随分格を落としたものだと思いましたが、処刑された彼の兄というのは剥奪されたものの侯
爵の称号を持っていたらしい。大公妃はいくらなんでも無理だろうが侯爵夫人なら悪くないだろう、そんなことを伯父
はぶつくさという調子で話していました。アレクセイはそんな伯父に、「所詮貴族の称号に弱いブルジョワ」と言葉を
返したらしい。初めてアレクセイという若者に共感しました。その頃私は伯父の秘書のようなものでしたが、伯父がそ
んな風に政治ごっこに夢中な分若いなりに事業を掌握していると己惚れていた。伯父がしっぺ返しを食らったというこ
と自体が痛快でした。ええ、つまり私も若かった。肝心のシューラがどう感じたかということがすっぽり頭から抜け落
ちていた。言い訳めきますが、それくらいシューラとアレクセイの組み合わせは私にとっては想定外だったんです。シ
ューラは女王然といつまでもヴァシーリィ島の屋敷にいるものだ、なんとなくそう思っていましたね。
動乱の1905年、と今なら言えます。けれどその当時私たちは砲声と希望に包囲されて無我夢中だった。仕事も政治も
プライドも恋も……そう、恋だったんでしょう……何もかもが一直線に私たちを追い立てていた。1年後、死体が積み
上がり、都市は廃墟になり、国会は開かれても皇帝の権力はむしろ強化された。アルラウネは姿を消し、アレクセイは
……そう、そういえば私は驚かなかった……モスクワの反乱分子の一人としてシベリアに送られることになりました。
シューラは変わった。当然です。アルラウネのような女性が通り過ぎた後は、何もかもが元通りではいられない。え
え、私はそう思っていた。アレクセイのことも、彼との縁談のことも、つまりはそんなに大事なことだとは考えていな
かった。アルラウネの強烈な存在感に幻惑されていたんです。恋に恋していたシューラは、伯父があてがった王子様ア
レクセイに娘らしい好意を持っただけだと思っていた。Loin des yeux, loin du coeur(目から遠ければ心からも遠い)
……とフランス人なら言うんでしょうね。これを教えてくれたのはシューラの家庭教師だったフランス女でした。シベ
リアに送られた若者のことなど、伯父も私も忘れていた。シューラだけが覚えていたんです。そして母鳥が雛を孵すよ
うに胸の奥に大事に大事に温め続けていた……。
そんなことに、私はあの時まで気が付かなかったんです。あの、1917年の初夏まで。
――何を言う、わたしを導く運命など誰に分かる。 (ラシーヌ「アンドロマック」第1幕第1場)
↑
お気に召したら拍手をお願いいたします!
TOP
NEXT