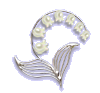 「新世界へ」
「新世界へ」Nach der Neuen Welt
作:ぼーだら
目を瞑るのは簡単だ。
それだけで、彼女の体の、心の中に彼の響きが満ちる。この小さな部屋に、彼がいたときの音楽
が、歌が、他愛ないおしゃべりが、くぐもった囁きが溢れかえる。ああ、目を瞑るのは簡単だ、け
れども瞑れば、今度は開けるのがつらい。
机の上いっぱいに、彼の手書きの譜面が広がっている。そう、目なんか瞑らなくてもいい。彼の
響きは、いつだって彼女の中にあるはず……。
彼のヴァイオリンをもう一度構えた。彼女の姿勢を直そうとした彼と、そのままじゃれ合いにな
ってしまったのは…3日前? 「ここまでが宿題だからな」って、おどけた声を出してそのまま出て
行ったのは2日前? せっかちな彼が散らしたインクのしみだらけの譜面。「俺は練習曲は嫌いだっ
たなぁ。でも兄貴がさ……」無音の瞬間を避けるみたいにしゃべり通しで、それでも彼女のために
昔弾かされた練習曲を記憶を頼りに書き出してくれたアレクセイの長い指。その少し前、彼女の髪
を、肌を滑っていた指……。
練習曲第1番。Allegro Moderato sereno……ふん、と声が出た。セレーノ、晴れやかに。「練習
曲にそんな指示があるもんか」。……言い捨てて弓を絃に当てる。晴れやかに。それが彼の希望、
だから。Eの音が低い。ペグを回し絃を締める。何かが狂っていたのだ…。
タン、と硬い音を出して、絃が切れた。
そして彼女はここに来た。「グリスマン商会:楽器・譜面・その他」。ふと振り返ると、通りを
渡ってゆくズボフスキーの背中が見えた。そう、ずっと前、ズボフスキーと可憐なガリーナと、ア
レクセイと4人でここを通ったときにこの看板を見覚えたのだった。可哀想なガリーナ、そして気の
毒な……。聞いたことのない、不思議なリズムが店から流れ出したのはそのときだった。
我に返り、彼女は店のドアを押した。リズムはさらに大きく、陽気に彼女の回りに渦を巻く。ス
タッカート、和音、すべてが風変わりで、ぎくしゃくして、なのに調子がよくて楽しげだ。思わず
ブーツの爪先が、とんとんと床をたたきそうになる。リズムは揺れ、メロディは跳ね上がる。口笛、
鼻歌、指拍子がよく似合う。
「おや、とんだ不調法を」ピアノの向こうから、鬚面とよく光る1対の目が飛び出した。
「いいよ……聞かせてもらって面白かった。風変わりだけど楽しい曲だね」
「おお、分かっていただけますか!」今度は黒服に包まれた小柄なからだが躍り出た。
「アメリカの曲なんですよ。『ジ・エンタテイナー』、スコット・ジョプリンの曲です。ねぇ、信
じられますか、アフリカの生んだ大作曲家なんですよ!」
「あ、あふりか?」
「ええ、ほんの少し前まで奴隷だった人々が、今新世界の音楽を書いてるんですよ!」
店主は、彼女に抱きつきかねない興奮ぶりである。「奴隷だった人々が!!」
「今は、アメリカの音楽が一番進んでいるんです! ティン・パン・アレーをご存知ですか? ニ
ューヨーク中の音楽家が集まっている場所なんですよ。いや、世界中だ。アフリカ、イタリア、そ
れにユダヤ人たち……そして世界で一番新しい音楽が生まれている!」
黒い丸い小さな眼がくるくると回りキラキラと光り、まるで御伽噺の子鬼である。
「ピアノ譜をお求めですか、お客様? 1枚で、古臭いロシアの街がぴかぴかのブロードウェイに変
わること請け合いです! ピアノだって喜んでくれますよ、躍り上がってね!」
「…ピアノが喜ぶ?」「請け合いますよ!」「躍り上がられちゃ大変だ。こっちが潰れるよ」
店主は笑う。それこそ躍り上がるような笑い声。「確かに! 確かに!」
彼女も笑った。「ヴァイオリンなら躍り上がったって大丈夫だね。絃はありますか?」
「ああ、ヴァイオリンですか! ええ、ありますよ! グリスマンは何でも持ってますよ! お待
たせしません、どれです? E線? A線?」「E線です」
スキップするように、店主はカウンターの後ろの戸棚に向かった。ピアノの脇には、手書きの譜面
が散らばっている。あの店主は作曲まで手がけているのだろうか? まるで印刷されたかのような
美しい譜面である。
「はい! これです!これですよ!」また子鬼のように、店主がひょっくりと現れた。譜面をそそ
くさと掻き集め、後ろに押しやり、ひどく近くから彼女の目を見つめ返してきた。「A線もD線も
G線もお持ちしましたよ。予備に一そろいいかがです?」
アメリカ……彼女は、多分その国を知らない。事故で記憶を失っているから、はっきりしたこと
はわからないけれど。けれども、あの店主、グリスマン氏の話を聞いていたら、そこはまるで音楽
の溢れる天国みたいだ。ティン・パン・アレー。不思議な響き……ひどく騒々しそうで、なのに楽
しそうで。フィンランド湾のはるか西には、そんな名前の街があって、陽気な人々が日がな歌って
過ごしているのだろうか? そんな街なら、シベリアでの苦役で傷んだアレクセイの指も今一度、
かつてのように絃を歌わせるのかもしれない…ずっと昔彼女がドイツで聴いていたように、失われ
た記憶の中にある旋律を。せつない夢に落ちかけて、ふと彼女は目を覚ます。あの譜面。
アレグロ・モデラート・セレーノ。メロディはたどたどしい。なんとか音符は追っているものの、
音は心細げで、一小節ごとに居場所を忘れて立ちすくむ。迷子のような音の群れの中に、弾む音を
聞いて彼女は立ち上がる。ヴァイオリンが落ちる。ドアが開く。
「ただ…」
「おか…」語尾は接吻の中に消えた。
アメリカ。彼女はその国を知らない。でも分かっている。彼のいる場所が彼女の新世界だ。
彼の新世界は遠い。その遠い血塗られた道を、彼は今必死で、命がけで辿っている……。

