
―第3章―
なつ様
彼と君の母上が再会したのは本当に偶然の奇跡だったと思います。
監獄に送られる仲間を奪還するために待ち伏せた先で、偶然君の母上と再会したそうです。
彼が再会した時、母上は17歳より以前の記憶がありませんでした。母上はロシアに来てから、何らかの事情で記憶を失くして
しまったようです。もっとも彼はその事情をうすうす気づいていたようでした。
かつての恋人と再会したものの、彼はその手を取ることを選ばず、記憶を取りも出させドイツに送り返すと決めていました。
少しでも記憶を取り戻すきっかけになればと、ヴァイオリンを弾いていました。しかし、監獄での強制労働のために、彼の指
は以前のように自由に動かすことが出来なくなっていたようです。途中で曲が途切れるのを何度も耳にしました。私は音楽の
ことはよく分かりませんが、彼がヴァイオリンをとても愛していたことは知っていました。
君の母上は私の妻が面倒を見ていました。母上はロシア貴族の邸で7年近く暮らしていたようで、市民の生活に慣れるのに少
し時間を要したようです。ここでの生活に慣れるのに従って、私の妻とも打ち解け仲良くなっていったようです。妻は彼女の
悩みや不安などの相談を受けていたようでした。
そんな時、妻が憲兵に襲われ亡くなりました。母上は妻を犠牲にしてしまったと随分自分を責めていましたが、あれは仕方の
ないことだったのです。
それを目の当たりにした彼は、人として当たり前の感情や、人への愛情を改めて認識したのだと思います。妻の事件をきっか
けに、母上の手を取る決意を固めたようでした。
二人は間もなく結婚しました。
結婚後も彼は忙しく働いていたので、二人で一緒に過ごせる時間は少なかったと思いますが、それでも十分に幸せだったと思
います。
この写真を見て下さい。
そこまで一気に話していた初老の男性は、背広の内ポケットから1枚の写真を取りだした。
そこには一組の若い男女のカップルが笑顔で写っていた。
この写真は、二人が結婚の報告をしに党に来た時に撮ったものです。集合写真を取った後、同志の一人が偶然撮ったスナップ
写真です。
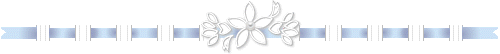
「おい、もう写真はいいだろ」
集合写真を撮影した後、新妻と談笑していたところを撮られた彼が、照れ隠しのためにわざと怒ったようにカメラを持った同
志に言った。
「すごくいい写真が撮れたと思うぜ。出来上がりを楽しみにしていてくれ」
同志は少し茶化すように答えた。
新妻は、はにかんだ笑顔を夫に向けて言った。
「どんな写真か楽しみだね」
春の日差しのように温かい空気に包まれた空間で、二人の結婚は周りの人々にも幸福を分け与えていた。
1週間後その写真は出来上がり、彼の手に渡った。
自信満々にシャッターを切った同志が言う。
「なかなか良く撮れているだろう?二人ともいい表情をしている」
「そりゃ被写体がいいからな」
照れもあり、彼は素っ気なく言葉を返した。
その写真を懐に入れ、彼は数日ぶりの家路に着いた。
「今帰ったぜ」
「おかえりなさい。疲れているでしょう?こっちで休んで」
「いや、大丈夫だ。それより、ほら土産だ」
彼はそう言いながら、懐から写真を取り出した。その写真を見るなり彼女は眼を輝かせ、満面の笑みを浮かべた。
「ぼく、こんな風に笑っているんだ。素敵な写真だね。二人の写真なんて撮れないと思っていたからすごく嬉しい。宝物にす
るよ」
彼女は写真を胸に抱えたまま、しばらく離さなかった。
憲兵の取り締まりが厳しくなって来たこの時期、写真を部屋に飾ることは危険だった。
彼女は1冊の本の中に写真を入れ、夫が帰宅できない時、寂しさを紛らわすために何度もその写真を見ていた。
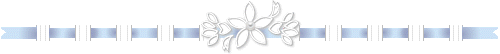
この写真は二人にとって宝物だったと思います。この写真があったことで彼女は随分慰められたことだったでしょう。
二人が結婚して4年ほど経った頃、彼女は身ごもりました。栄養失調で弱った体を心配した彼が、妻を自分の実家に預けたの
です。
私は彼から「妻が身ごもり体が弱っているので、あるところに預けている」と打ち明けられました。私のほか、信用できる極
わずかな同志にしかこのことを伝えていませんでした。しかし、預け先までは彼から打ち明けられていませんでした。が、お
およそ預け先の察しはついていました。彼が貴族出身であることは周知の事実でしたから…。
ところが、何処からかの誤った情報に煽られた民衆が、彼の実家を襲いました。彼の祖母と旧侯爵家に残っていた僅かな使用
人たちが犠牲になりました。しかし彼女は何とか難を逃れましたが、その行方が分からなくなってしまいました。その頃の彼
はとても憔悴していました。大切な肉親と身重の妻を、自分が解放しようとしている民衆に襲われてしまったのですから…。
その後、彼女の手紙が届き彼女が無事であることが確認できました。
その手紙の内容から、彼は同志の一人が裏切り者ではないかと気づきましたが、自分で妻を迎えに行くことを決意しました。
罠もしれないと思いながら…。
私は彼に言いました。危険だから女性の同志に迎えに行ってもらうように、と。
しかし彼は譲りませんでした。
“たったひとりでこのロシアまで、見つかるかどうかさえわからないおれを追ってきてくれたあいつに対して、おれはまだ1
度もお返しをしてやってないんだよ”と。
これが彼の最期の言葉になりました。
彼は妻と産まれて来る新たな命と共に、生きるために命がけで迎えに行った。そして罠にかかり命を落としました。さぞ無念
だったことでしょう。革命の成就を見届けることができず、何よりも大切な妻を一人ロシアに置いていかなければならなかっ
たのですから…。
そして私自身も激しく後悔しました。なぜあの時もっと強く彼を引き止めなかったのか、と。この思いは一生涯消えることは
ないでしょう。
最後の言葉を呟いた時、初老の男性の眼には涙が浮かんでいた。少女の顔から色がなくなり、鳶色の瞳が潤んでいた。下まぶ
たギリギリまで涙をため、懸命にそれが瞳から零れるのを堪えている。真一文字に結んだ唇が小刻みに震えていた。
3人はしばらく沈黙した。
そこの空間だけ別世界のような、重苦しい空気が流れていた。
不意にカフェのドアが開き客が入って来た。外からの少し冷えた新鮮な空気が流れ込み、重苦しい空気が流されていく。
客は空きテーブルを探すことなく、3人のテーブルを目がけて近づいて来た。
 ←NEXT
←NEXT ←BACK
←BACK