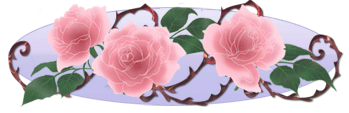
光
―第1章―
なつ様
ホームに降り立った時、何故か少女は「故郷に帰って来た」という感覚にとらわれた。
自分の血の中には、半分はロシアの血、もう半分はドイツの血が流れている事は、もの心ついたころ周りの大人から知
らされていた。
生まれたのはロシア。けれど、少女の記憶にロシアの想い出はひとつもない。
彼女は産まれてすぐ母親から引き離され、戦争も革命も無縁な場所で手厚い保護を受け、大切に育てられた。
少女が10歳の誕生日を迎えた時、母親の実家であるアーレンスマイヤ家に引き取られた。
少女の母親が亡くなったのは、彼女がアーレンスマイヤ家に引き取られる4年前のことだった。母親の友人たちが、少
女の存在を知り、懸命にその消息を追った。そしてやっと見つけた時、少女は10歳になっていたのである。母親譲りの
金髪と美貌。友人たちは一目で少女が旧友の娘だと分かった。
少女はあまり多くを語らなかった。ただ、ロシア語もドイツ語も堪能で、父親譲りと思われるヴァイオリンの才能がず
ば抜けていた。
彼女のヴァイオリンの才能を聞きつけたザンクト・ゼバスチアンの教師の強い後押しにより、セバスチアンは開校以来
初の女子の入学を異例で認めた。
「君のお父上の才能はよく知っているよ。本当にすばらしかった」
教師は口々にそう言った。そして必ず付けくわえられる言葉が、
「わが校始まって以来の自由奔放な、型破りな生徒だったよ」
別の教師は彼女の母親の事を
「綺麗な金髪、眼を引く整った容姿。とにかく目立つ生徒だった。在学中は女性だとは気づかなかったが、言われてみ
れば奇異な存在だったな」
図書室の片隅に、歴代の学生の写真が飾られていた。その中の1つに学生時代の両親の写真があった。
「これが私のお父様とお母様・・・。私はやっぱりお母様似だったのね」
伯母や両親の友人が言うとおり自分は若い頃の母親に瓜二つだった。そして父からはヴァイオリンの才能をもらった。
−1933年、少女は16歳になっていた。
ゼバスチアンに入学して6年の歳月が過ぎた。ヴァイオリンの才能を認められ、ロシアの楽団からの招きで、少女は初
めて父親の祖国の地を踏むことになった。
音合わせの合間に街に出た。革命から16年。街はすっかり様変わりして、その名もペテルスブルクからレニングラード
に変わっていた。
少女はその街を歩きながら、両親のことを思った。父の祖国、そして母にとっても第2の祖国。
母がこの国に来たのは16歳。今の自分と同じ年である。あの混乱の時代、命の危険を顧みず見つかるかどうかさえ分か
らない父を追ってきた。
2人はどんな経緯をたどって再会し、どのように生きたのだろう。
何故母は、私を手放したのだろう。
−私は母に捨てられたのだろうか?−
ずっと心の中で思っていたこと。このロシアで、その謎が解けるのだろうか・・・?
レニングラードの街並みにコンサートのポスターが貼られていた。
−マリア・ミハイロヴァ−
その名前と共に少女の写真があった。
一人の初老の男が足をとめた。彼は思わず声を挙げた。
「ユリウス!」
−いや、違う。ユリウスではない。ならば・・・。死産と聞かされていた、あの時の子どもか?名前、年頃、何よりも
ユリウスにそっくりだ。
この少女に会わなければ・・・!
初老の男性は、その年に似合わぬほどの速度で歩き、ある建物の1室のドアを叩いた。
ドアが開き住人が顔を出した。30代半ばの男性。彼が貴族の家柄を捨てボリシェビキに入党したのは、大切な同志が亡
くなる直前の事だった。
彼に今し方見てきた真実を告げた。彼は革命時の混乱に乗じてロシアを出国する、自身の姉と同志の妻を確認していた
が、このことを「ずっと言えないでいた」という。
ただ彼も、「子どもは連れていなかった」と言った。
初老の男性は自宅に戻ると本棚の扉を開き、1冊の本を手に取り、そこから1枚の写真を取りだした。
少女の両親の写真。そこには1組の夫婦が、この上なく幸せそうに映っている。
初老の男性は16年前のことを思い出していた。
あの日大切な同志が撃たれ、ネヴァ河の流れと共にその身体は流されてしまった。彼を探すと共に、その妻の居場所も
探した。彼の妻と身ごもっていた子どものことが心配だった。だが、どんなに探しても、彼女の居場所は分からなかっ
た。子どもに関しては何件もの医師に当たり、「それらしい女性の出産に立ち会ったが、子どもは死産だった」という
証言を得た。
初老の男性はこの証言を信じたくなかったが、彼の妻もその子どもも見つけ出すことが出来ない以上、これを信じざる
を得なくなった。
−あの写真の少女は、間違いなくあの2人の子どもだ。
生きていたんだ。生きていてくれたんだ。
翌日初老の男性は楽団のリハーサル会場に出掛けた。少女に面会を申し込んだが、リハーサルを理由に断られた。しか
し彼は諦めなかった。リハーサルが終わるまで粘った。
白夜の季節をとうに過ぎた8月下旬のロシアは、日が暮れれば10度以下になることもしばしばで、この日もそうだった。
“お疲れ様でした”−遠くでそんな声が聞こえてきた。
その声に懐かしさを覚えた。同志の妻と同じ声に聞こえたからだ。
いきなり外国人の老人が声をかけたら、異国の少女は驚くだろう・・・。だが、躊躇している暇はない。今会わなけれ
ば、今度いつ会えるか分からない。
初老の男性は意を決して少女に声を掛けた。
「失礼、マリア・ミハイロヴァさん?私はあなたのご両親の友人でフョードル・ズボフスキーといいます。あなたにお
話ししたいことがあります」
予想通り、少女は驚いた表情でこの男性を見た。
「どうしたんだ?マリア」彼女の後ろから声がした。現れたのはドイツ人の長身の男性。
「おじさま、この方が私の両親の事でお話ししたいことがあるって・・・」
「失礼。マリアの伯父のダーヴィトといいます。ぼくも一緒に伺っても構いませんか?」
マリアに通訳をしてもらいながら、伯父は同行を求めた。
初老の男性は彼女の伯父の瞳をしっかりと見据え、静かに頷いた。
少女と彼女の叔父、そして初老の男性はネフスキー通りの大きなカフェに入った。
多くの人々でにぎわうカフェ。整った身なりの人々が集まっている。ロシア時代では考えられない光景だった。世界恐
慌の最中、このソビエトはその影響を受けず、経済成長が盛んである。カフェはその現実を如実に表していた。
先に口を開いたのは少女の方だった。
「あなたは私の両親を御存じなのですね?」
「ああ、知っている。ところで君のお母さんは今ドイツにいるのかね?」
「母は10年ほど前に亡くなっています。私は産まれてすぐ他人に預けられ育ったので、母のことは何も知りません」
「ユリウスが亡くなった?ああ、なんてことだ!」
初老の男性はそう言ったきりしばらく口がきけなかった。
「私は父も母も知りません。だから知りたいのです。母が何故私を手放したのか、父が何故亡くなったのか、を!」
店員が飲み物をテーブルに運んできた。彼は注文していたウォッカを一口くちに含むと、一気に飲み込み大きく息を吸
った。
「今から話す事は、君の両親の真実だ。だが、その真実の中にはとても厳しい現実がある。それでも、聞く勇気はある
かい?」
「もちろんです。誰も教えてくれなかった両親の真実が知りたい」
「分かった。では話そう」
初老の男性は自分の知っている2人のすべてを話そうと思った。
 ←NEXT
←NEXT ←BACK
←BACK