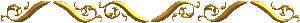

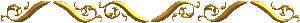
「Lilium Auratum 〜 輝きの百合」
作:ぼーだら
私たちは一緒だった、私は覚えている/夜を打ち破り、ヴァイオリンは歌っていた
いつもいつも、あなたは私のもので/どんなときも、あなたは美しかった
(A・A・ブローク「私たちは一緒だった」より、藤井宏之訳)
<1909年7月>
「あ……」唇から、思わぬ囁きが洩れた。
甘く胸苦しい香気の霧が彼女を包む。脳髄が震えるような、優しい痛みが背中を駆け下りる。目の奥が熱く
なり、何かが零れそうになる。
「……どう、したの、ヴェーラ?」優しいソプラノの声が彼女に尋ねた。
「……驚い、たわ……」彼女は背筋をぴんと立てて、優雅にサロンの中央に進み出た。
「随分香りが強いことね、この百合は」
山々の緑を溶かし込んだ青空のような、高麗写しの李朝青磁の大ぶりの花瓶に、子供の頭ほどもある大きな
百合が数輪ゆったりと生けてある。くるりと反り返った幅広の花びらの中央に黄色い筋が走り、その周りに
散った赤い斑点も相まって大きな星が花の中央で輝いているようだ。華やかで清雅な姿だが、香りは息苦し
いほどに甘く、強い。
「見たことがない花だわ」
「今朝、ここの温室で咲いたって」「温室で?」
あ、と今一度声が洩れた。ヨーロッパにはない大きく香り高い東洋の百合。星をいただく黄金の百合、緑濃
い日本の山のみに生まれる、そう、Lilium Auratum。
彼女は指を伸ばし、花瓶の肌に走らせた。顔を近づけると、胸を占める甘い香りが体の奥まで染み透るよう
な感覚が走る。この花瓶、と無理に思い出してみた。朝鮮の王妃が親しかったロシア公使夫人に送ったもの
だといっていた。そして王妃は、王宮で日本人たちに惨殺され……鉄の焼けるような血の匂いが、花の香り
に入り混じった気がする。そうだ、血の匂い…そう、この花は結局そこに行きつくのだ。
「あ、レオニード?」兄が入って来たらしい。彼女は、後ろを見ないようにしてサロンを出た。この花の前
で、兄と言葉を交わすつもりにはなれない。
<1906年9月>
「貸しなさい」令嬢の強い言葉に、新しく来たばかりの庭師のマトヴェイは、広い肩を寄せるように縮こ
まった。「わたくしが植えます」「お嬢様が?」
なぜそれだけが残っていたのだろう? 前任者の形跡は髪の毛一筋も残さず消去されたはずの広い庭、朱に
染まって鉄と血の匂いを放つ骸は言うに及ばず。
「温室の中央花壇の準備はできているんでしょうね?」「はぁ、もちろんでございますが」
庭師の手からひったくった球根は、彼女の手のひらにすっぽり収まるくらいの大きさだ。球根を包んでいた、
不思議な文字を散らした新聞がはらりと冷たい土に落ちた。
「移植ごてを」球根の鱗茎を手早くほぐす。磨いた爪が汁にまみれて色を変える。べたつく汁がレースの袖
口を汚す。「本当に綺麗な花が咲くんだよ」……そんな声を聴いた気がして、ひどく腹が立った。
「こてはまだなの?」「ただいまお持ちします!」ざくり、ざくりと、刃物を立てるように土にこてを刺した。
「もういいわ、お行き」涙を見られないためではない。ヴェーラ・ユスーポヴァは、そんな甘い感傷を己に
許しはしない。9月の温室はまだ夏の名残をとどめているにしても、あの12月が現実だ。
温室の外で、やや日に焼けた男の指が落ちた新聞を拾い上げていた。
<1905年12月>
若者一人に、どうしてこんなにたくさんの血があったのだろう?
風はいよいよ激しさを増し、降りだした雪も明日にはヴァーレンキ(フェルトの長靴)が埋もれるほどに積
もることだろう。だがこの血は残るのではないか、そんな気がした。兵士たちは黙々と遺骸を古毛布に包み、
周囲の雪を均している。庭師の小屋の捜索は明日になるのだろう。警察を呼ぶことになるのだろうが……。
「終わりました」「ご苦労」部下の報告に、ロストフスキイ中尉は反射的に答えた。
屋敷は森閑と静まり返り、一筋の明かりも漏れてこない。始末を彼に任せておいて、上官はもうやすんだの
だろうか? そうではあるまい。
「カレリン曹長、それでは兵をまとめて戻ってくれ。明日は通常勤務だ」
カレリンの無骨な瞳にわずかに疑問がよぎった気がしたが、それは無視した。確かにこれは近衛兵の仕事で
はない。だが、質問を許すわけにはいかないのだ。「どうした、行け」
警察に余計なことを言われないように、小屋は封印しておいた方がいいだろう。開け放った戸の前に積もっ
た雪をどけようとして、英語が書かれた木箱に気が付いた。見覚えがある。アースキン商会、ロンドン。中
にもう一つ木箱があり、そちらには「Louis Boemer Co.Yokohama」とあった。中を探ると、漢字らしきもの
の書かれた新聞紙の中に、何かの球根が入っている。いや、こちらではない。ロンドンのアースキン商会の
方だ。目立たない中規模商社だが、イギリス外務省、というより日本の息がかかっていた。日露戦争中、革
命派が密かに発注してフィンランドから運び込もうとした武器を扱ったのも確か……。ロストフスキイ中尉
は今夜のすべてが飲み込めた気がした。
庭師を装った革命派の若者、エフレムは無用心にも、アースキン商会を通し自分も球根を取り寄せていた
のだ。あるいは、ロンドンや同志との連絡をカモフラージュするつもりだったのかもしれない。イギリスは、
世界中の園芸植物の集散地でもある。だが、屋敷の主レオニード・ユスーポフがロンドンからの荷を怪しん
だとき、彼の命運は尽きた。そしてレオニードは、最近ヴェーラが急に園芸に興味を持ち出したことに思い
至ったに違いない。近衛兵を私兵のように使ってやみくもに処分を急いだのは、妹を圏外に置くための強硬
策……この球根が、あの男の形見になったな。中尉は今一度、雪に散った血を思った。
★作品中に引用したブロークの詩は、ショスタコーヴィチの作曲で「A.ブロークの詩による7つの歌曲」と
して親しまれているものです。2013年にこのSSを書いたときには、「藤井宏之」氏のサイトから日本語
訳を引用したのですが、現在このサイトは閉鎖されているようです。不正確な表現になっているかも知れ
ません。皆様のご教示をお待ちいたします(管理人)。
↑
お気に召したら拍手をお願いいたします!
NEXT
TOP