|
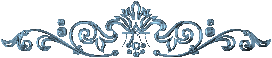
空ゆくものよ
Der Himmelreiser
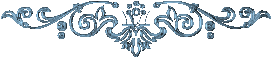

このSSは、相互に関連の薄いいくつかの話が並行して進む構成になっており、それぞれが話ごとに色分けされた短い文章
の「箱」として並んでいます。色ごとに読んだら一つながりの話になり、順番に読むこともできます(多分)。一つ一つの話
は、それぞれあるオルキャラが中心で、白い箱は全体の共通項になる事件についての話になっています。
参考文献:的川泰宣著『月をめざした二人の科学者―アポロとスプートニクの軌跡 』(中公新書)
筆者:ぼーだら
始まり:彼は、とうに足音に気付いていた。
|
|
|
|
「ここだと思った」彼女の声はいつも明るい。「トルーディが心配していたわよ」
「さすがだね」そういいながら、彼は動こうとはしなかった。むしろ優しい笑顔を彼女に向けて、
細い指先でちょい、ちょいと差し招くような仕草をした。
「危ないわよ」声に苦笑がにじむ。「よくここまで入れたものね」
「そりゃあ僕は」「ザンクト・ゼバスチアンの〝ぬし〟だから」「ご名答」
石造りの古い壁はひんやりと、秋の冷気を吐き出している。北東の空にまだ曙光は遠く、一夜を
守った街の灯は疲れたように緩く瞬きしているようだ。耳を澄ますと、これだけは昔と変わらぬ
レーゲン川の水音まで聞こえてくるのではないか。
ゆっくりと、彼女が傍に来ていた。湿りを帯びた石の床を注意深く進み、電気を切った懐中電灯
を拾い上げる。ゴチック型式の石の窓枠に手を置くと、何百年分かの冷たさと温かさが掌に滲み
込んでくる。
「オルフェウスの窓、ね」
|
|
|
|
窓ガラスに映る妻は、冬のガウンの上から大きな毛織のショールをぐるぐると巻き付けていて、
そんな風にしていると絵本の中の農婦のようにも見えた。夫の視線に気が付くと目元だけで少し
笑い、「あなたは寒くないの?」と尋ねてくる。
「うん、大丈夫だ。さっきの酒が残っているのかな、顔なんかむしろ火照っている」
「却ってよくないわよ」「心配性だなぁ」
この季節となれば、ロシアの夜は凍えるようだ。人を締め付けてくるような大気の向こう、星々
はこちらを睨むかのように厳しいくっきりとした光を放っている。
「わざわざ見に起きたのね?」「君こそ」「さっきも見たでしょうが」「お互い様だろ」
小競り合いのような軽口を交わしていると、本当に体が温まってきたような気がした。
|
|
|
|
「生徒たちは揃いましたかな、マドモワゼル・デピネ?」
おもむろに振り向くと、若い教師は驚いてわずかに身をそらせた。
「ええ、ムッシュー・ボワン、行儀よく待っています」「何人ほどです?」「67人」
「おや、そんなにですか」教頭は、大げさなため息をついた。
「正直、私は今でも反対ですよ。親御さんに知れたら、あまりいい顔はされますまい」
「校長先生は、すぐに賛成してくださいましたけれど」
「さあ、何よりそれに納得がいかない」二人はなんとはなしに足音を忍ばせていた。
「あの方が一番反対されるものと思っていたんですがね」「大賛成でしたわよ」
教師はこれ見よがしに胸を張った。
「最先端の科学にはいつだって高い関心を持っておられる方ですもの。女子にも正しい科学知識は
必要というのもご持論ですわ」
「いや、でも、あの方のご出身がご出身だからね……」
教頭はほっと溜息をついた。「まあ仕方ないでしょう。マダム・ブサックを起こさねばなりますま
いね。人数分のコーヒーを頼まないと」
|
|
|
|
主任はそこにいた。
シベリアで壊血病を患い、歯をすべて失ったことはよく知られていた。だが、そんなことを感じさ
せないほど彼の笑顔は自然で、そして星のように輝いていた。人生の最良の瞬間に立ち会った人の
笑顔だった。
|
|

|
|
「ここからは、ロシアの空が見えるそうだ」「前にも聞いたわよ、それ」
彼女は、窓枠に半ば腰掛けるように体を半回転させた。淡い星の光に照らされていた顔がすっぽり
と影に入り、横顔の線だけが薄く闇に浮かび上がる。目の色も髪の色も消えてシルエットだけにな
ると、その横顔は彼の愛した女たちにあまりにもよく似ていた。
美人演奏家として名の知れた女である。だが、彼の目からすれば甘い華やかさでは彼女の母親の
ほうが勝っていたと思う。そして気品や威厳という点では、死んだ妻にはやはり及ばない……。
「君のお父さんとお母さんは、この窓で恋に落ちたんだ…」
|
|
|
|
「そろそろ外に出ない? 見逃しちゃったらつまらないわ」
夫は優雅に一礼し、気取って手を差し出した。
「では奥方様、一曲お願いできますかな?」「喜んで」妻も嫣然と微笑みそれに手を重ねる。小さ
なテラスが舞踏会の会場ででもあるかのように、二人は寄り添って進み出た。青年将校と年若い書
店主。若き外務官僚とその秘書。小さなヴェーロチカの両親。大使館員夫妻。
星は輝き、寒気の中で時が揺らぎ、思い出の長い時間の中で二人は肩を寄せて空を見上げていた。
|
|
|
|
講堂は、クスクス笑いと少女たちの期待でほんのりと温かかった。
「はい! 皆さん! こちらを向いて!」ジャニーヌ・デピネが、パン!と手を叩く。それだけで
穴に潜り込む兎さながらおしゃべりも忍び笑いも姿を消すのだからしつけの良い娘たちではある。
「では観測会を始めます。時間が来るまでに説明をします」
青、茶色、黒、様々な色の瞳が一斉にジャニーヌを見つめている。瞳だけではない、少女たちの国
籍は大西洋の両側に広く散らばっている。それぞれ「良家の子女」と呼ばれるような家庭の娘たち
だ。壁に大きな太陽系の図を掲げる。扉のすぐ前に、いかにも苦虫をかみつぶしています、という
雰囲気を濃厚に漂わせた副校長の姿がある。校長は来ていないのかしら、と会場に目を走らせた。
|
|
|
|
特製の台の上には、昨日まで「疾駆する馬のたてがみのようにアンテナを後ろになびかせた優美な
球体」があったのだ。びろうどに包まれた、一点の曇りもなく輝き渡る銀色のあの姿をもう目にする
ことはないのだな、と思うと不思議な感傷が胸を浸した。
|
|







