
―最終章―
なつ様
少女は父の形見のストラディバリウスを顎にかけた。首にできたヴァイオリンだこは、ヴァイオリニストの勲章だ。
身体の成長と共にヴァイオリンのサイズを変えてきた。10歳の時にストラディバリウスを渡されたが、その時の少女には体
格と技術が伴っていなかった。時期が訪れるまで、ストラディバリウスは大切に保管されていた。
今、少女は16歳。
6年間、音楽学校できっちり学び、ストラディバリウスを弾きこなせるほど技術は成長している。そして、身体も心も少女
から大人へと変わりつつあった。
今回の演奏旅行が決まった時、少女は初めてストラディバリウスを弾こうと思った。6年間封印していた大切な楽器を机の
上に置き、ヴァイオリンケースから宝物を扱うように大切に取り出した。
初めてストラディバリウスに触れた瞬間、その感触は何とも形容し難いものがあった。
まるで自分を待っていてくれたような感覚。柔らかく温もりがあった。初めて触れるのに、なぜか懐かしささえ感じた自分
に驚いていた。
ストラディバリウスの音色は光り輝く音色をしている。弾けば弾くほど優しい音色で自分に語りかけてくれる。まるで父の
愛に包まれているような感覚だ。
そのストラディバリウスを手に、父の祖国ロシアで初演奏をする。正式に招待されたコンサートホールでの演奏会。学校の
定期演奏会とは違って、自由奔放に音を繰り出す訳にはいかない。自分はどうも父の血を継いだらしく、その日の気分で音
を操ってしまうところがあるらしい。教授にも伯父にもよくそう言われる。今日はその血を封印しなければならない。
さすがに大きな音楽ホールに立つと、緊張感は否めない。
目を瞑り、大きく深呼吸をして弓を構える。
ベートーベン ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章
「春」は、躍動感と希望に満ちた曲だ。ベートーベンが、耳が聞こえなくなってから作曲したとは思えないほどエネルギッ
シュで軽快な曲。
少女が初めてこの曲を奏でた時と、両親が「オルフェウスの窓」で運命的な出会いをしたことを知ったのは、ほぼ同時期だ
った。彼女のイメージの中でこの曲は、両親が互いの楽器を奏でながら愛を囁きあっている、「清々しい愛の曲」といった
イメージを受けた。きっと母がピアノ伴奏をしたのなら、父のヴァイオリンと向き合いながら、それでも情熱的に演奏した
のだろうと思った。
父もこのストラディバリウスで演奏したことのある「春ソナタ」。
今、自分の持っている最大限の技術と魂を込めて....。
ストラディバリウスからは、彼女がその時感じたままの「自然な音」が放たれていた。ストラディバリウスと少女はひとつ
となり共鳴し合った。彼女はヴァイオリンと一体となり、夢中で演奏し終える。
「ブラボー」の声と、鳴りやまない拍手が彼女を現実に引き戻した。
客席には、初老の男性と老女の姿があった。そしてもう一人、少女の父に憧れて入党した若き同志。彼は、自分が知る二人
の忘れ形見の成長した姿に、限りない喜びを感じていた。
彼らも才能に満ち溢れた若きソリストに惜しみない拍手を送っていた。
演奏会は大成功のうちに幕を下ろし、ロシアは少女の華々しいデビューの出発地となった。
ロシア出発の朝、少女は一人ネヴァ河沿いを歩いていた。両親もきっと二人で歩いた、この河沿い。橋の欄干に肘を掛け、
流れを見つめる。
ポケットからそっと母の形見を取りだし、ネヴァ河に小さく束ねた金色の髪を流した。
父が撃たれ、流されてしまったその身体はついに見つからなかった。この河からもっと先に続くフィンランド湾のどこかで、
静かに母を待っているような気がした。ならば、最愛の母と一緒にしてあげたい。
少女は静かに流れていく金色の髪を見届けた。
「ここにいたのか、マリア。何をしていたんだい?」
伯父は少女に声を掛け、彼女の隣に並んだ。
「「お母様の形見の一部をネヴァ河に....。お父様と一緒にさせてあげたくて」
伯父は河を見つめたまま、しばらく何かを考えているようだった。
伯父が態勢を変え、欄干に片肘をつき少女の方に向いた。いつも開いているのか、いないのか分からないくらい眼を細めて
いる伯父が、珍しくその眼をしっかり開けていた。
「彼女だって守りたかったはずだよ、彼の命を。彼女も命がけで叫び、彼を救いたかった。けれど、“窓”の伝説には抗え
なかった....。
でも、一方で君のお母様は伝説を打ち負かしたと思う。あの時、彼女は階段から落ち、全身を打ちながらも無意識のうちに
お腹をかばったのだろう。大切な小さな命を守りたいという母の強い愛情が、“窓”の運命を撥ね退けたんだと僕は思う。
だから君は無事に生まれ、今、自分の人生を生きている」
「そうね・・・。両親の生涯のすべてが“窓”の伝説どおりの悲劇では無かったと、私も思うわ。写真に写っている笑顔を
見ると、二人は本当に幸せだったのだと思う。だって、二人にしか出来ない素晴らしい恋を成就させたんだもの」
「君の言うとおりだね。二人は、一生に一度の激しい恋を成就させた。他人が入る隙が全くないくらいのね。残念ながら僕
も太刀打ちできなかったよ」
最後は冗談っぽく言う伯父に、少女はクスッと笑って見せた。
「ロシアは美しい国だね。1年のうち半分は雪に閉ざされ陰鬱とした雲に覆われる中で、短い夏は本当に輝いて、人々を生
き生きとさせる。君の両親はこんなに綺麗な街で暮らしていたんだね」
少女は河を見つめ、微笑んで「ええ」と短く答えた。
――私、ロシアに来て良かった。
両親は強く信頼し合い、深く愛し合っていた。様々な困難があった中でも、未来への希望を失わず、二人で共に支え合いな
がら生きていた。
そして、産まれて来る私を心から愛してくれていた。それをしっかりと実感できる。
今ほど両親の愛を感じたことはない。
少女はネヴァ河を見ながら、心の中でそっとロシア語で呟いた。
――お父様、お母様、私をこの世に送り出して下さってありがとうございました。お二人が成し遂げられなかった夢を私が
叶えていきます。
どうか見守っていて下さいね。
そしていつか、お父様とお母様のように、私も一生に1度の激しい恋をする時が来るのだろうか....?
少女の心は、ロシアに来て大きく成長した。
10歳まで他人に育てられた彼女は、自分のルーツを知らずに生きてきた。物心がつく年齢になる頃、少女は周りの子どもと
は異なる家庭環境にいることを知った。
乳母や使用人は皆優しかった。物質的には何ひとつ不自由なく暮らすことができた。ヴァイオリンも習うことができた。け
れど、少女が心の底から欲していたものを、誰も与えてはくれなかった。
肉親の愛情を知らず、また、自分が何のために生まれて来たのか、自分の存在価値が分からなかった。
両親のこと、自分の出生時のことを知りたい。押さえきれない強い欲求が父の祖国に足を向けさせた。
母がこの国に足を踏み入れた時の年齢と同じ16歳になった少女。
少女にとっても今回ロシアを訪れたことは、運命に導かれた必然的な出来事だったのかも知れない。
鳶色の瞳に映るネヴァ河の流れは、これからも変わることなく上流から下流へと流れていく。それは過去から未来へと永久
に流れる時のように....。
少女の穏やかな横顔を見ながら、伯父は再び細い目で問いかけた。
「ところで、楽団からの誘いの件はどうするつもりなんだい?」
少女はネヴァ河から視線を外し、伯父の眼を見て言った。
今回の演奏公演で成功を収めた少女に楽団側から、ロシア留学の打診がきていた。
「急に言われたから、驚いてしまってまだ決めかねているの。でも、まだゼバスチアンで学ばなければならない事がたくさ
んあると思うし....」
「一音楽関係者としてはとてもいい話だと思うよ。君の素晴らしい才能をもっと伸ばすいい機会になる。....まぁそうは言
っても、君がロシアに行ってしまうのは僕も伯母さまも寂しいけどね」
少女は再び河の流れを見つめていた。その眼はネヴァ河と対話しているかのように見えた。
不意に視線を伯父に向ける。その鳶色の瞳には強い光が宿っていた。
「ストラドは、今はドイツの空気の方が合っていると思うの。ドイツの空気は、私の望む音を響かせてくれる。お父様やお
母様に包み込まれるような愛情を感じて、とても優しく穏やかな気持ちで音楽を奏でることができる。....でも、いつか私
がもっと成長した時、ロシアの方が合う時が来るかも知れない。だから、その時までは伯父さまと伯母さまのスネをたくさ
ん齧らせてもらうわ」
「大歓迎さ!!」
伯父は片目を瞑りウインクして見せた後、この国に来て初めて大声で笑った。つられて少女も声を出して笑った。
しかし伯父は近い将来、少女が羽ばたいていくことを予感していた。何せこの少女には、あのクラウス・ゾンマーシュミッ
トの血が流れているのだから....。
一抹の寂しさを振り切るかのように、明るく少女に声をかける。
「さあ、帰ろうか」
「ええ、帰りましょう。レーゲンスブルクへ」
二人はネヴァ河沿いの道を歩き始めた。
不意に柔らかい風を感じ、少女が振り返った。
「どうした?マリア」
「何でもないわ」
そう答えながら、少女は確かに感じていた。温かな両親の眼差しを....。
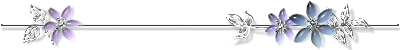
「いい娘に育っているね」
「ああ。きっと良いヴァイオリニストになるさ。おれの子だからな」
「ふふっ。ぼくの子でもあるよ」
空高くから、鳶色の瞳と碧い瞳が優しく見守り続ける。
 ←CODA
←CODA  ←BACK
←BACK