アレクセイの温かい腕から離れ、ユリウスはベッドから身を起こした。服を身につけ、最後にゲオルクスターラーを首に
かけた。
記憶を失う前からこのペンダントだけは自分と共にあった。このペンダントが自分にとって、どういう由来のものである
か分からなかったけれど、何故かとても大切なものだという確信のようなものがあった。ずっと身につけているゲオルク
スターラーはすっかり彼女の身体の一部になっていた。
アレクセイはベッドの上から彼女の様子を眺めていた。ふと、彼が口を開く。
「それ、随分大切にしているんだな」
声を掛けられた彼の方に振り向き、ユリウスは答える。
「うん。このゲオルク・スターラーだけが、ぼくの過去と今を繋いでいる唯一のものだから……」
そう答えながら、襟もとからゲオルク・スターラーを引き出し見つめた。
アレクセイも身を起こし、彼女が引きだしたペンダントを初めてしっかりと見た。
ドイツにいた頃の記憶を手繰り寄せる。彼が知っている限り、彼女がペンダントをしていた記憶はない。もっとも彼女は
夏でもシャツの第1ボタンをはずしていたことがなかったので、実際には身に着けていたのかどうかは分からない。
――聖ゼバスチアン時代――。
純粋に音楽にのめり込めた4年間。そしてユリウスと過ごした最後の1年。
思えば聖ゼバスチアンに編入してから3年もあの窓に登ろうと思わなかったのに、どうしてあの時登ってみたのだろう…。
あそこに登ればロシアの空が見られると思ったからか?
兄貴を思い、感慨に耽っている時ユリウスが下を通った。もともと気になる存在だったあいつが、カーニバルのあの時、
女だと知った。その瞬間彼女が運命の恋人となり、今、人生を共にしている。
ゼバスチアンのことを思い出している時に、ふとゲオルクスターラーを思い出した。
-これと似たようなものを、確かゼバスチアンで見た気がする。誰か同じものをしていたのだろうか?
そう考えていた時、ユリウスの首からゲオルク・スターラーがはずれ床に落ちた。
「あっ……!」
小さな声をあげ、彼女は慌ててペンダントを拾おうとした。アレクセイも同じ様にそれを拾おうとベッドから身をのり出
した。わずかに彼の方が早くペンダントに手が届き、彼女に手渡そうとした時、アレクセイは思い出した。同じペンダン
トをしていたピアノ教師のことを。
あれはユリウスが編入して来るわずか10日程前のことだった。
クラウスをはじめ、寄宿舎の生徒が校庭でボール遊びをしていた。彼はボールを蹴りながら味方の生徒に指示を出してい
る。少年たちの楽しそうな様子にピアノ教師が声をかけた。
「クラウス、私も仲間に入れてくれないか?」
声をかけけられたクラウスは、声の主も見ずに答えた。
「かまわないぜ、ヘルマン・ヴィルクリヒ。ちゃんと勝利に貢献してくれるなら……な」
ふふっ、と小さく笑い、ヘルマンは上着を脱ぎ捨てた。シャツのそでをまくり戦闘モードになってボール遊びに参加した。
ヘルマンは30代半ばのピアノ教師だ。ピアノばかり弾いていてロクに走れないのでは……と、クラウスは途中参戦した助
っ人にあまり期待していなかった。ところが、その期待をいい意味で彼は裏切った。クラウスが思っていたよりもこのピ
アノ教師の動きは機敏で、しなやかだった。
ボールがクラウスに繋がりゴールした。味方の生徒や彼らを応援していた観客の歓声が聞こえた。それに気を良くしたク
ラウスが右手を突き上げて歓声に答えた。振り向くとヘルマンもクラウスと同じポーズを取っていた。二人、眼と眼を合
わせ頷き合う。
二人の息の合ったプレイが功を奏し、クラウスのチームが勝利した。
ヘルマンは、少し上がった息を整えながら、校庭の隅に置いてあるベンチに腰掛けた。
クラウスがヘルマンの正面に立ち、タオルを差し出した。それを受け取りながら、楽しそうにヘルマンが言った。
「約束は守っただろう、クラウス」
「ああ、確かにな。遊びでも勝利は気持ちいい」
そう言いながら、クラウスはヘルマンの隣に腰かけた。
「ピアノ教師なのに、結構動けるんだな」
「私はそこらへんのピアノ教師とは違うんでね」
わずかに棘を含んだ言葉にヘルマンは乗らず、軽く受けながした。
クラウスはこの一風変わったピアノ教師、ヘルマンがなぜか好きだった。彼の何処かつかみどころのない雰囲気が、自分
に少し似ているから気になるのかも知れない。
――どことなく自分に似ている。
クラウスは、あまり他人の事情など詮索するタイプの人間ではなかったが、ヘルマンのことには少し関心があった。彼も
音楽にどっぷりつかっているようで、その実それがすべてではないように感じていた。
自分と同じような明るさを持ちながら、ふとした瞬間に見せる深い影を、クラウスは敏感に感じ取っていた。クラウスの
視線に気が付き、ヘルマンは正面から彼を見つめ返した。そのびろうどの瞳に吸いこまれるような錯覚を覚え、クラウス
は彼から眼をそらした。年の差なのだろう。学生の自分とは違い、ヘルマンには大人の余裕があった。
「さて、疲れも取れたから私は戻るよ」
そう言いながらベンチから立った時、彼の首から何かがすべり落ちた。ベンチに座っていたクラウスの方が先にそれを掴
んだ。手のひらのものを確かめる。コインのようなものをあしらったペンダントだった。ヘルマンは少し慌てたような表
情をした。
「悪いね、クラウス」
そう言いながら、彼からペンダントを受け取った。
クラウスは、そのピアノ教師に似つかわしくないペンダントのことが気になった。
「あんたにしては、随分安っぽいものを持っているんだな」
何の悪気も含んでない言葉に、ヘルマンは苦笑した。若さゆえの遠慮のない、どこか残酷な言葉だった。ヘルマンは静か
に口を開く。
「私が君くらいの年の頃に、1度だけオルフェウスの窓に登ったことがある。その時に下を通りかかった女性を見てね…
…。彼女はクリームヒルトと名乗って、最後まで本名を教えてくれなかった。ある日突然、彼女はこの町から姿を消した。
これは、その彼女との…、思い出の形見だよ」
ペンダントの由来を聞いてクラウスは、自分の無遠慮な言葉を恥じた。
「悪かったよ、さっきはあんな言い方をして」
「気にするな、普通はそう思うさ。こんな古い安物のペンダントを大切に持っている人間なんて、そうそういないだろう」
ヘルマンは大人の余裕を見せた。クラウスは、彼の表情に小さな憧れを抱いた。父親の記憶のない彼にとって、身近な大
人は聖ゼバスチアンの教師か、たまに会う祖国の同志しかいなかった。亡くなった時の父と似た年頃のヘルマンに、記憶
のかなたに消え去りそうな父親の姿をだぶらせる。
クラウスは興味深げに聞いた。
「どんな女性だった?」
シャツの袖を戻しながら、ヘルマンは答えた。
「碧い瞳、綺麗な金色の髪の美しい女性で、きれいなソプラノの声だった。彼女にこのペンダントを渡した時、涙を流し
て喜んでくれたよ。…けれど、それが最後だった」
クラウスはヘルマンと眼を見合せた。まだ本当の恋を知らない自分には、理解できない領域だった。
「何でこんな事を話しちまったのかな?ボール遊びに興じて、あの頃の自分に戻ってしまったのかな。つまらない昔話だ。
忘れてくれ」
ヘルマンはそう言うと、首にペンダントをひっかけ、その場を立ち去った。
クラウスは、しばらくベンチに腰掛けたまま、ヘルマンの後ろ姿を見送った。
――それから数週間後――。
午後の授業はつまらないからサボろうと決めて、教室には行かなかった。時間つぶしのために行く場所として、人の多い
談話室や自習室はいやだった。現実から離れたかった。
中庭から見上げた先に、オルフェウスの窓があった。
――あそこなら静かだろう。授業中だ。あんなところにきっと誰も来ない。
ただ一人になれる場所が欲しくて、クラウスは階段を上がった。
窓から外を見る。遮るものがない窓からの景色に、なぜか心が落ち着いた。遠く続く空を眺めながら、ふと故郷を、兄を
思い出した。
一人になると、いやでも思い知らされる。聖ゼバスチアンの学生と自分は明らかに違うということを。ここにいる自分は
本当の自分ではない。誰にも負けないくらいに音楽を、バイオリンをこんなにも愛しているのに、その道に進むことは決
して、無い。
やりきれない気持ちになった。どうすることもできない怒りと悲しみを上手く消化することができず、感情が溢れ出よう
としたその時、下から澄んだきれいな声が聞こえた。
「何をしているんだい?クラウス」
声の主は、先日編入してきたくそ生意気なピアノ科の5年生、ユリウス・フォン・アーレンスマイヤだった。
瞬間、涙を見られたと思った。それを隠すように、平然と答えた。
「ここに登ったのは初めてだ。女なんか通るものか」
ユリウスが困惑したような、少し驚いたような表情になったのを特に気にも留めずにいた。そんな心の余裕がなかった。
あの時は、複雑な感情を自分でもどうすることもできなくて、彼女との一件はすっかり記憶のかなたへと遠のいていた。
そして、ピアノ教師の「オルフェウスの窓」にまつわる、あのペンダントの事も。
再び思い出したのは、カーニバルのリハーサルの日だった。
――ユリウスがクリームヒルトの衣装を身につけ、皆の前に初めて現れた時――。
「クリームヒルト!」
そう叫んだピアノ教師の声を、クラウスは聞き逃さなかった。
確かに、あの場にいたほとんどの生徒たちが、ユリウスの姿を見て、みな一様に驚いていた。けれど、ヴィルクリヒだけ
は違う意味合いの表情だったような気がした。
感嘆の声や歓声を上げる者はいたけれど、誰もユリウスを見て役柄の名前を叫ぶ者はいなかった。
あの時彼が叫んだ「クリームヒルト」という言葉は、ユリウスの役柄に対してではないように思えた……。
――もしかしたら…。あの時ヴィルクリヒが叫んだ「クリームヒルト」は、ユリウスの母親の事か?彼女の母親だとすれ
ば、年頃もヴィルクリヒと変わらない。たしかユリウスの母親は、ヴィルクリヒが学生の頃レーゲンスブルクにいたはず
だ。同じ街にいたのだから、あの窓で出会っても不思議じゃない。
「アレクセイ?」
ユリウスが不思議そうな顔をして声をかけた。その声に、はっとして彼女の碧い瞳を見た。
「どうかしたの?」
「いや……」
答えを誤魔化したまま考え続けた。
――まさか、……な。金髪に碧い眼の女性はレーゲンスブルクにだってゴマンといる。そんな偶然があるはずがない。
一度は自分の考えを否定したアレクセイだったが、ユリウスの姿の向こうに、何故か彼女の母親の姿が見えた。ゲオルク
スターラーに視線を移し考える。
――……けれど、もしかしたら……。
アレクセイはペンダントを握りしめながら、再びユリウスを見て言った。
「これは、おまえにとってとても大切なものかもしれない。これからも大事にしろよ」
ユリウスは、急にそう言われて驚いたけれど、これまでと同様に大切にしていこうと思った。
「うん。ありがとう」
明るく答え、彼から大切な宝物を両手で受け取った。
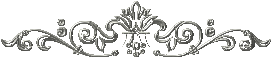
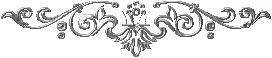
 ←BACK
←BACK
