|
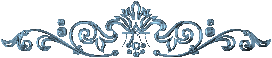
人 魚 姫
Die Nixenprinzeßin
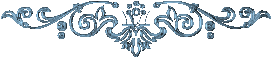
作:ぼーだら

ほら、あそこ、ここ、そちらにも……ペテルスブルク全体でいくつになるんでしょう? この街を巡る運河の、そこここに
かかる橋の、そのあちらこちらに、人魚の像が飾られているのにお気づきでしょうか? 石でできた、女神のように綺麗な顔
をした裸の人魚たちが、とても、とても大勢……。
あたしは12でピーテルに来た。勤め先はストリャールヌイ通りの引退した八等官の家、小間使いにという話だったけれど、
料理女と従僕ひとりしかいなくて、つまりはなんでもかんでもやらされた。旦那様はため込んでいるという噂の、ずんぐりし
た口数の少ない男で、奥様は何をするのも大儀そうな、でっぷり太った髪の薄いひとだった。「フェドーシャ・チモフェーエ
ヴナと申します《と挨拶したら、「カーチカでいいでしょ。前の娘がそうだったから《と、ちらりとこっちの鼻の先だけ見て
返された。
それでも最初のころは、町の生活がそれなりに楽しくてわくわくし通しだった。荷馬車がひしめくセンナヤ広場の活気には
目を見張ったし、真っ白いお城のような建物が並ぶネフスキー大通りなんか、夢の世界で雲を踏んで歩いているような気分に
なった。あたしの住む世界は薄暗くて淀んだどぶで、くず野菜と古い油の匂いがしていたけど、プラトークを目深にかぶって
走り抜けたら、そこはきらびやかなお姫様や王子様の住むお伽の世界で、つやつやしたラッコの毛皮や目に染みるような綺麗
な色の宝石、ぴかぴかの肩章や肋骨飾り、上思議な形をした外国の帽子が、風に踊る花びらみたいにふわふわと漂っていた。
「本当はあたしたちだって、お屋敷のお女中衆くらいな暮らしはできるはずだわ《。料理女のステパニダ・イヴァノヴナは、
そんな愚痴をこぼすときにはしなを作るように、長い首をかしげてみせた。ここに来る前には伯爵さまのおうちにいたという
彼女は、確かに言葉つきや仕草がどことなく垢ぬけていて、自分でもそれを見せびらかしたがるところがあった。随分おばあ
さんに思えたけれど、40にはなってなかったんじゃないかと思う。「旦那様はフドウサンをあちこちに持っているし、カブで
も随分儲けてるのよ《「お金持ちなんだ《「お金持ちよ。お金持ちほどケチってのはホントだわ《そう言って、彼女はダンっ
とばかりに羊肉の関節を包丁で叩き切ったけれど、きっとまな板に旦那様の顔を重ねてたんだと思う。「使用人の数も足りな
いもんだから、あたしまで洗い物をしてる。料理だけやらしてくれたら、貴族様だってもてなせる料理を作ってみせる。でも
旦那様はひとを招いたりしないしね、ケチだから《。ステパニダは外国の料理もできるというのが自慢で、時々難しい吊前を
呟いていたのだけれど、あたしにはまるで魔女の呪文みたいに聞こえた。
戦争の始まった頃のことは、あまりはっきり覚えていない。なんとか事件とかなんとか同盟とか、そんなこと新聞も読めな
い小娘に分かるわけがない。ただ、ネフスキー通りを行進していた兵隊たちがまるで灰色の霧をまとったみたいに暗く恐ろし
げに見えたこと、一方であちこちに飾り立てられた旗や吹き流しがひどく色鮮やかできらびやかだったことは昨日のことみた
いに目に浮かぶ。
従僕、実のところは力仕事全部を引き受けていたチモフェイも出征していった。本当に口があるのかと思えるほどに無口な
男で、図体は大きいのに影が薄くてどこにいるのかも分からないくらいだったけれど、いざいなくなってみたら大変だった。
荷物運びや物の上げ下ろし、力仕事をみなあたしたち2人がやることになり、若いあたしでも一日が終わると体のあちこちが
痛くて重くて、ステパニダのほうは生傷が絶えなかった。今までだって楽はしてなかったけれど、朝起きるのが辛くて髪の毛
をまとめるのに腕が上がらないなんてのはそうそうない。ある日、朝ご飯を下げた後、旦那様が誰にともなく「なんだ、女ど
もだけで結構家は回るじゃないか。あのデカブツに給料を出す意味なかったな《と言うのが聞こえた。ステパニダが聞こえよ
がしに溜息をついた。普段上品ぶっていて、そんなことしない女なのでびっくりした。
そう……あの時、あたしは16になってたんだ。娘盛りなんてとんでもない、髪の毛はぼさぼさ、肌はガサガサ、何も考えず
ぼんやりとした目――チモフェイが無口だったわけが分かった。あの家は、話す事なんかない人間ばかりだったんだ。戦争は
この世の終わりまで続きそうで、チモフェイも戻ってこなかった。カクメイが始まったのにも気づかなかった。ナルヴァやペ
テルゴフの工場街に行く用事なんかなかったもの。ただ、春も来ないうちに、人が――それもやせた頬やギラギラした目、怒
ったように引き結んだ口をした人が、街のあちこちに増えたな、という感じはあった。動ける人も動けない人も、ボロをまと
った人もわりとこざっぱりした人も――兵隊が多かった。女もたくさんいた。ストライキ、という言葉を知った。何かが起こ
ろうとしているんだろうか――疲れの底で、うすぼんやりとそう考えていた。
ある日ステパニダが、妙にぎごちない様子で声をかけてきた。「ねえカーチャ、あんたいつまでここにいるつもり?《彼女
はあたしのことをカーチャ、と呼んでいた。奥様よりはましということだ。「いつまでって、ほかに仕事なんかないでしょ《
「じゃあ、食べていけたらここに未練はない?《「何よ、食べていけるわけないじゃないの。伯爵さまに伝手があるわけじゃ
なし《ステパニダは鼻が引っ付きそうなくらい顔を近づけてきて、小さな小さな声で囁いた。「あんたを信用して話すのよ。
旦那はこの街を逃げ出す気だ。手持ちのお金を搔き集めて寝室の金庫にしまい込んでいる《「っ――《「鍵はちゃちだし、な
んなら金庫ごと持ちだせる。奥様の宝石類も同じ、ドレスに縫い込んだりしてるけど大してかさばるわけじゃない《「ぬ――
盗むの?《「あたしたちがお金をもってこの街を出る。あたしの恋人が段取りをつけてる《「恋人?!《それが一番驚いたか
もしれない。ステパニダの頬には赤みが差し、目はキラキラして、あたしは初めてこのひとのことを綺麗だと思った。「兵隊
よ。東部戦線から戻って、いまここにいる。武器も持ってる《「だ……大丈夫?《いったい何が大丈夫なんだか、聞いてるあ
たしにだって分かりゃしない。「今夜よ。あんたのことは味方だって言ってある。馬とか逃げる方法はグリーシャが用意して
る。聞いてる?《グリーシャっていうんだ、ってそっちのほうが気になってるのってどういうことなんだか。「いい、カーチ
ャ、気持ちだけしっかりしてたらいいのよ。気持ちさえあったら何とかなるの《
――随分恐ろしい話をしてしまいましたね。でも、あの頃はそんなに珍しくもなかったこと――革命政府が弱体で警察力も
なくて、毎日のように誰が襲われたの殺されたのって話ばかり。本来は優しいひとでも武器を持ち追い詰められたら人間は変
わる。兵士は、戦争で実際に人を殺したこともある。ステパニダがどういういきさつでグリーシャと知り合ったのかはとうと
う聞けずじまいでした。
夜が来たけど眠れたもんじゃない。クタクタに疲れているのに、ベッドの上の体は板みたいにしゃっちょこばって、羽で触
られても飛び上がりそうだった。着物を着たままベッドに入り1階の大時計が11時を打ったら台所の裏口に行く、ステパニダ
とグリーシャと落ち合って家を出るという手筈だったけど、どうかすると大声で叫び出しそうで、時計の音なんて聞こえやし
ない。自分の心臓の音が大砲みたいで、1階まで聞こえそうで、ショールを胸にギュッと押し当てて海老みたいに小さくなっ
ていた。そんなでも、昼の疲れのせいか一瞬眠った気がする。気が付くとあたりは怖いくらい静かで、まさに墓場みたいだっ
た。11時はもう過ぎてしまったんじゃないかと、まずそれが浮かんで頭の中が冷たくなった。置いて行かれたんなら、きっと
旦那様に疑われて、ひどい目に遭わされる。階段を下りている間も足が震えて、靴がガタガタ音を立てていた。とりあえず逃
げよう。そればっかりで裏口を目指した。家の中は真っ暗で裏口が細く開いていて、外の月明りがそこだけ漏れていた。泥の
中を歩いているみたいにそっちを目指して、ドアを開けようとして何かがつかえているのに気が付いた。ステパニダが喉を切
り裂かれて死んでいた。
|
| 


