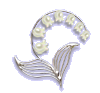 「立会花に寄せて」
「立会花に寄せて」5月の明るい陽光が深い色合いのビロードのカーテンの隙間から忍び込み、ユリウスの白い頬を照らす。
頬に日差しの暖かさを感じたユリウスは、長いまつげに縁取られた青い瞳を開き、太陽の光を認めると上体を起こし微笑んだ。
昨晩床に入った時は小雨が降っていたため、雨が降ったら外に出ることは許されないので今朝は晴れるかどうか気が気ではなかっ
た。
ガウンを羽織り確認のためにバルコニーに出てみる。
昨晩の雨に打たれた木々の葉が朝の日差しを受けて一層その美しさを増している。
ユリウスはその美しい風景を満足気に眺めながら、朝の新鮮な空気を腕を広げて胸いっぱいに吸い込んだ。
そして、この特別な日の始まりを一人で迎える淋しさを感じながらも、かすかな期待を抱き部屋の中に戻り、アレクセイの祖母で
あるヴァシリーサの嫁入り道具の一つであった豪奢な鏡台に向かう。
「おはよう。昨日の雨が上がって今朝は素晴らしい天気だよ。後で外に行こうね」
鏡に向かいお腹に手を当てながら、まだ見ぬお腹の子に声を出して話しかける。
まるで返事をするかのような胎動を感じる。
鏡に映る自分の顔は何と幸福に満ち足りているのか…。
アレクセイと再会して、ただひたすらアレクセイの訪れを待ち不安に怯えていた頃の自分の顔と何と違うことか…。
あの頃、こんな幸福がやって来るとは思いもよらなかった。
記憶を失った僕には彼との再会は、僕がドイツから追いかけてきたと聞かされた反逆者アレクセイ・ミハイロフとの初めての出会
いであった。
それなのに、彼の広く温かい胸に抱かれ、切なそうに僕を見つめる鳶色の瞳を認めた瞬間、彼への愛がほとばしる様に僕の胸に広
がった。
それは、記憶を失ってから誰にも感じたことのない感情だった。
僕はひたすら彼の愛を求めた。
彼を愛することだけが僕がユリウスとして確かにこの世に存在したことを知らしめ、彼を愛することによって僕が存在することが
許される気がした。
僕が求めれば、アレクセイはレオニードと同じ様に僕の手を取って温めてくれると思っていた。
でも、アレクセイは違った。
彼は再会した時に抱き締めてくれただけで、その後はよそよそしかった。
僕がレオニードへの連絡を頼んだことがアレクセイを怒らせたので、レオニードのことは心配だったけれど彼の前でレオニードの
名を口にしないことにした。
もしこのままアレクセイの元を去ったら、もう二度と彼と会えなくなってしまう、また心の暗闇の世界に戻ってしまうと思うと彼
の傍を離れたくなかった。
僕は彼と共有していた過去を思い出したかった。
アレクセイもそれを望んでいる。
それなのに思い出そうとするともう一人の僕が「思い出すな」と僕の耳元で囁き、頭が真っ白になってしまう。
思い出したいのに…思い出せればアレクセイは僕を愛してくれるのにと何度思ったことだろう。
彼を愛したということ以外には何も思い出せずアレクセイの足がだんだんと遠のいていくのに、それに反して僕の心は彼のことで
いっぱいになっていく。
そんな求めることしかしなかった僕にガリーナが教えてくれた。
愛する人の立場や思想を理解し、寄り掛かるのではなく自分の足で立って寄り添う愛、ガリーナとズボフスキーとの傍にいて僕は
何を見ていたのだろう。
自分の想いしか考えずに、この国の実情やアレクセイたちが目指すものに眼を向けたことがあっただろうか。
僕もこの国のことを知りたい、アレクセイの目指すものを知りたい…という思いがふつふつと湧き上がって来る。
その矢先にあの惨劇が起こった。
今ガリーナと同じように愛する人の子を宿し、その喜びや生まれてくる子に託す彼女の気持ちが手に取るように分かる。
我が身とお腹の子を犠牲にして僕を守ってくれたガリーナ。
あの夜、「もう離さない」と僕を抱き締めてくれた時のアレクセイの言葉、その言葉の重みが今実感として胸を締め付ける。
ユリウスは浮かんでくる涙をこらえながら再びお腹に手を当て、
「君はアレクセイや僕に生命を託した人たちの思いを繋いでいくんだよ」
と言い聞かせるようにつぶやいた。
そして、意を決するように立ち上がるとヴァシリーサがユリウスのために新調したドレスの中からこの日に着ようと心待ちにして
いた白いドレスに手を通した。
それは、好きな花を聞かれ『すずらん』と即答したユリウスを歓喜させた裾にすずらんが一輪大きく刺繍された白いサテンのドレ
スであった。
一目見てこの日のためにあるようなドレス、まるでヴァシリーサが孫夫婦の記念日を分かっていて誂えたようにユリウスには思え、
思わず涙が出るほど嬉しいものだった。
**********
 *************
************************
アレクセイは事務所の窓辺に立ち薄いカーテンを引き、5月の明るい日差しに目を細める。
窓を開け両手を大きく伸ばし、朝の少しひんやりとした空気を胸いっぱい吸い込んだ。
徹夜してどうにか予定通り報告書を仕上げることが出来たことに満足を覚えながら、これで今日ユリウスに会いに行き、久々に朝
まで一緒にいられるかと思うと知らず知らずのうちに口元がゆるんでしまうアレクセイだった。
机の上の書類を整理し終え帰り支度をした時、勢いよくドアが開き同志のイワンが息せきって飛び込んできた。
「ああ、良かった!!間に合った!!」
「そんなに慌ててどうしたんだ?」
「政策委員長のニキータが過労で倒れてモスクワに行けなくなったんです。それで副議長である同志アレクセイが代わりにモスク
ワに行くようにとのことです」
副委員長のイリヤだけに任せられないという議長のニジェンスキーの判断だとアレクセイは理解した。
「分かった!それで、ニキータの容体はどうなのか?」
「安静にしていれば大事には至らないとのことです」
「それは良かった!!で、俺は何時の汽車に乗ればいいんだ?」
アレクセイは「ユリウス、許してくれ!!」と心の中で詫びながらイワンに尋ねた。
「事前交渉はイリヤが行いますし、本会議は明日の午後なので夜行で良いそうです。切符と会議資料を用意しておきますので、午
後8時に事務所に来て下さい。それまでは、ゆっくりと休むようにとの議長ニジェンスキーのことづてです」
ニジェンスキーには何週間も前に今日一日だけ休暇をと願い出ていたので、その心遣いが身に沁みた。
貴族の実家に預けている女房に会いに行くとは口が裂けても言えなかった。
後ろめたさのために休暇の理由をはっきりと告げることは出来なかったアレクセイに、
ニジェンスキーは理由を追求することなく「若手期待のアレクセイに倒れられては困るからな。一日ゆっくりと休めよ」と快く許
し肩をたたいてくれた。
アレクセイはニジェンスキーの寛大さと包容力のある温かさに深く感謝した。
こうなれば時間を無駄には出来ない。
アレクセイは足早に事務所を後にした。
花屋が開くまでは待ってはいられないので、朝の市場で買うために広場に向かう。
店出しをちょうど終えたところで、木桶を逆さにして腰掛け煙草をくゆらしている花屋のおやじに声をかける。
「そこのすずらんを花束にしてくれ」
「へい、旦那。朝帰りですかい。それじゃ、奥方への詫びに花束ですか?」
「まあ、そんなところだ」
おやじと長話をしたくないアレクセイは素っ気なく答える。
「このすずらんは摘み立てで、まだ朝露が残っているんですぜ」
おやじがアレクセイに花束を手渡しながら言うと、店先の5月の風に揺れる可憐な白いすずらんに見入っていたアレクセイは思いつ
きを口にした。
「おやじ、もう一束つくってくれ」
「旦那、よっぽど奥方を泣かしているんだね。これですかい?」
ニヤニヤしながら小指を立て、アレクセイを見やる。
「馬鹿を言うな!俺は女房一筋だ!!早くもう一束つくってくれ!!」
「そんなに怒らんで下さい。冗談ですよ!」
朝帰りするのに女房一筋なんて珍しい男だと小声でブツブツ言いながら、新しい花束をつくり始めた。
女はユリウス一筋だが、仕事のためにろくに会いにも行けず寂しい思いをさせ泣かしているのは事実なので、自戒してしまうアレ
クセイだった。
「出来ましたぜ、旦那。余計なことを言ってしまったんでサービスしておきましたぜ」
おやじは先程の花束よりも一回り大きな花束を差し出した。
喜ぶユリウスの顔を思い浮かべ
「ありがとうよ。おやじ」と礼を言い、僅かばかりの心付けと共に金を払う。
「怒らせてしまったのにすんませんなあ。すずらんの花言葉は『幸福の再来』でさあ。奥方とお幸せに!!」
アレクセイはおやじの言葉に片手を挙げて応え、二束のすずらんの花束をかかえ『幸福の再来』という言葉を噛み締めながらアパ
ートへの家路を急いだ。
アパートに着くとすずらんの花束をそっとテーブルの上に置き、変装用の鬘と髭をつけ、老人の衣装に着替える。
老人がすずらんの花束を二束も抱え歩いては目立つので、布を濡らして切り口を包み、大きな布袋に入れて傷まないようにそっと
抱えてアパートを出る。
ユリウスへの元へと逸る心を抑えながら、老人らしくゆっくりと歩を進めてゆくアレクセイ。
自ずと記憶を失くしたユリウスと再会してからの日々が蘇ってくる。
あの夜、7年ぶりに出会ったユリウスは姿形が昔のままなのに、記憶を失くしていた。
俺のことも思い出したのではなく、シベリア送りを宣告された時の姿を見ていて、顔と名前を認識したに過ぎなかった。
おまえは俺を愛していたことも、そのためにロシアまでやって来たことも忘れ、俺たちの敵であるユスーポフ侯爵に守られて7年間
を過ごしてきた。
おまえの口から「レオニード」とユスーポフ侯の名が発せられ、レーゲンスブルグで俺しか見ていなかったおまえが他の男を心配
する姿を眼にすると、自分でも今まで感じたことのない憤りを覚えどうしようもなくなり、おまえに怒鳴ってしまった。
極寒のシベリアで木に吊るされた時、おまえを巻き込んでシベリア送りにさせなくて良かった、おまえはあれから無事にドイツに
帰り幸福になったと信じ、不滅の恋人として俺の心の中に封じ込めた。
追ってきたおまえをふり捨て、出会わなかったと思って忘れてくれと願ったことが現実となったことに愕然とした。
その罰を俺は今受けていると感じた!!
それでもおまえは去って行かなかった!!
あれからユスーポフ侯の名を口にすることもせず、何とか過去を思い出そうと懸命に努力するおまえ。
そんなおまえを見ていると、心の中に封じ込めたおまえの想いが頭をもたげてきてしまう。
ガリーナにまた俺を愛し始めていると知らされても、俺はおまえにそれを問うことも出来なかった。
俺にはおまえを愛する資格はない!!
おまえを抱き締めてはいけないんだと自分に言い聞かせ、自分の意志ではどうにも出来ないおまえの想いに歯止めをかけるために
はおまえに会わないようにするしかなかった。
ミハイルの心中事件があり、ますますユリウスに向き合えなくなってしまった頃、あのガリーナの悲惨な出来事が起こった。
ユリウス、俺たち二人は何人もの尊い生命の犠牲の上に生かされた。
真摯に人生と向き合い、生命の限り生き続けねばならない。
おまえを二度もふり捨ててきたことをおまえに告白し、真正面からおまえと向き合い、おまえへの変わらぬ愛を告げよう。
おまえに初めてすずらんを贈った夜、おまえが俺だけのエウリディケで俺だけを待っていてくれたことを知り、俺はユスーポフ侯
に感謝した。
俺がふり捨てたために記憶を失くしたユリウスを守り支えてくれた。
彼の保護と愛情がなければ、ユリウスは生きてはいけなかっただろう。
彼への複雑な思いはユリウスと結ばれた今感謝へと変容した。
そして、『オルフェウスの窓』の悲劇の伝説を俺一人で背負う決心をした。
ユリウスと一緒に暮らしてみて、思い出したくない恐ろしいことがあった為に過去の記憶が封じ込められていることを確信した。
俺を追ってたった一人でこのロシアまでやって来たのだ。
つらく耐えられないことが起こり、どうしようもなくなって俺のところに来ようと思ったに違いない。
ユリウス、おまえは過去を思い出す必要などないぞ!!
窓の伝説は俺一人が一身に受け止めればいい。
おまえは今とこれからのために生きていけばいいんだ。
 *************
*************一階に降りると、愛犬のマクシムがいつものように玄関で寝そべりながらユリウスを待っていた。
「おはよう、マクシム。今日もよろしくね」
ユリウスが声を掛けるとそれに答えるように尻尾を振り、ゆっくりと起き上がる。
年老いた上に、生まれつき不自由な後ろ足のためによろめきながらも、裏庭のすずらんへの先導は自分の務めと自覚していて、い
つもはユリウスの後をついていくマクシムが身重のユリウスの前を行く。
木々の緑が眩しいほどのきらめきを放つ木立の中を白いドレス姿のユリウスは、5月の陽光を浴びながらマクシムの後をゆっくりと
進んで行く。
初めてアレクセイがすずらんを贈ってくれた時のことが自然と思い出されてくる。
あの時のアレクセイの言葉を僕は一生忘れないだろう。
「おまえは記憶を失う前も、記憶を失っても二度も俺を愛してくれた。おまえは記憶を失っても俺が愛したおまえだ。だから過去
を思い出す必要はない。俺もおまえと同じように二度おまえを愛しているぞ。俺たちは今とこれからを生きればいいんだ」
そして、いたずらっぽく笑い次の言葉を続けた。
「それに、おまえをふり捨てたことを思い出されたら、今度は俺が捨てられてしまうかもしれないしな…」
僕はアレクセイの胸に飛び込んだ。
彼のおもいやりが嬉しかった!!
過去を思い出したい、でも思い出せない…胸のつかえがすっと消えていった。
感慨に耽って歩いているうちに目的の木立の下の茂みにたどり着いたことを、マクシムが吠えて教えてくれる。
このまま進むとすずらんを踏みつけてしまうことに気づいたユリウスは、
「ありがとう、マクシム。今日はすずらんを摘む大切な日なのに危うくつめなくなってしまうところだったね」
と言いながら、しゃがんでマクシムの喉を撫でた。
マクシムがこの場所に初めて連れて来てくれた時はすずらんを見つけた喜びで思わず摘んでしまったが、その翌日からは摘まずに
幼い日のアレクセイがしたようにマクシムと共に眺めているだけにしていた。
アレクセイがすずらんを買ってくるのは結婚記念日だけである。
僕たちの生活が苦しいこともあるが、二人にとってはこの日のためにある花であり、一年一年二人で年を重ねていく愛の深まりの
象徴であったからこそ摘むのを控えていたユリウスであった。
ユリウスはマクシムから白い可憐な花を咲かせている数株のすずらんに目を移す。
すずらんの花は初めての日と同じように僕たち二人の立会いとなってこの日を毎年見守ってくれていたが、今年は無理かもしれな
い。
ペテルスブルクは騒然とした大変な時期で、アレクセイはとても私的なことに構っている時間などないだろう。
まして、妻は身重で貴族の実家に預けてあることなど同志の誰にも言えず後ろめたさを感じているだろう。
僕は元気になったらすぐアレクセイの元へ帰りたかったけれど、このお腹の子が丈夫に育つためとガリーナの悲しい事件の記憶の
ために、ここにとどめるアレクセイの思いが分かるから僕はここで丈夫な赤ちゃんを産むことに専念している。
おばあさまも本当の孫娘のように僕を慈しんでくれて、この子の誕生を心待ちにしている。
幸福と一抹の淋しさを感じてこの日を迎えるのかと思っていた数日前、マクシムがこの場所に連れて来てくれた。
オークネフの話でそれはアレクセイの両親所縁のすずらんであることを知って歓喜と共に胸が熱くなり涙がこみ上げた。
口には出さないアレクセイのすずらんに込める愛の深さを知ることが出来たことと、今年はすずらんの立会いは諦めるしかないと
思っていた矢先だったので喜びは一入であった。
これでアレクセイが来れなくても、僕がこのすずらんを摘んで飾ることが出来る。
たとえ一人でも、すずらんが今までと同じように立ち会ってくれる。
それもロシアの大地に咲くアレクセイの両親から僕たちに受け継がれたすずらんを自分の手で摘み取ることが出来るのだ。
この子を授かって自分がロシアの大地に根ざすことが出来た気がした上に、過去にこだわらない僕たちであったけれど、こうして
ちゃんと過去と繋がりそして未来へと繋げることが出来ることを知り、自分で摘み取るこの特別なすずらんがこれからの幸福を約
束しているように思えた。
だから昨日の雨には心配したけれど、今朝の太陽がどんなに嬉しかったことか…
そんなことを思いながら、ユリウスはすずらんを摘み始めた。
ミハイロフ邸に着いたアレクセイは裏庭に回り塀を乗り越えた。
裏庭には子供の頃よく森へ遊びに出掛けるために通った小道がある。
その小道をはずれた茂みにはマクシムと共に眺めたすずらんが咲いている場所があることを思い出しながら進んで行くと、その茂
みの中に金色の髪が5月の優しい風に揺れ佇むユリウスを見つける。
すると、ユリウスを見守るかのように足元に伏せていたマクシムがアレクセイの存在に気づき、尻尾を振りながらアレクセイの方
に顔を向けた。
それを見たアレクセイは手でマクシムを制して、その場所を動かないように合図を送る。そっと近づいてみると、白いドレス姿の
ユリウスは手には摘んだすずらんを持ち、木洩れ日を浴びている姿はまるですずらんの精のようで、思わず足を止め見惚れてしま
う。
はっと我に返り、このままの姿だと驚かせてしまっては大変なので、変装用の鬘と髭を取り、背後から足音をさせないようにそっ
とユリウスに近づく。
手にそれぞれすずらんの花束を持ち、ユリウスを後ろから優しく抱きかかえるようにして、二束の花束をユリウスの目の前に差し
出す。
振り返ったユリウスは花束の主の姿を認めると、摘んだすずらんを足元に散らしながらアレクセイの首に腕を絡ませる。
「アレクセイ!!来れたんだね!!」
「ああ、どうにか仕事をやっつけてきたぞ!!この場所はマクシムが連れて来たのか?」
「うん。そうだよ」
「そうか。ありがとうな、マクシム」
アレクセイは大きな手でマクシムの頭をクシャクシャと撫でると、マクシムは主人の懐かしい動作に嬉しくなり、目を細めアレク
セイに身を寄せる。
ユリウスもマクシムに感謝するためにマクシムを挟んでアレクセイと並びマクシムの背を撫でる。
「本当にお手柄だったよ。マクシム」
マクシムは愛する二人に感謝され撫でられ、この上ない幸福を感じつつまどろんでしまった。
「それで、身体の調子はどうだ?」
会えた喜びのあまり涙をためているユリウスの青い瞳を覗き込みながらアレクセイは尋ねた。
「うん、大丈夫だよ。この子も順調だよ」
お腹に右手を当て、左手で涙をぬぐい笑顔をつくりながら答えるユリウス。
「徹夜したんだね。眼が赤いよ。今仕事が終わったって言ったよね!ひょっとして休暇が取れて朝まで一緒にいられるの?」
頬を上気させて問いかけてくる。
「そのつもりでいたんだが、同志の急病で代わりにモスクワに出張だ。今夜の夜行で発つ」
「そう…」
残念な声を出したユリウスだが、すぐに明るい調子で言葉をつなぐ。
「夜行なら早めの夕食まで一緒にいられるね。おばあさまと三人で久しぶりに食事がとれるね。大変な時期なのに来てくれてあり
がとう!!すずらんの花束もありがとう!!今年は凄いね!二束もあるんだね」
「こいつに俺たちのところに来てくれたお礼がしたかったんだ。俺たちの幸福に立ち会った花を知って欲しかったしな」
ユリウスのお腹に優しく手を当てながら答えるアレクセイ。
「そうだね。僕たち夫婦への大事な授かり物だよね!!」
ユリウスはアレクセイの手に自分の手を重ねる。
「すずらんが運んで来てくれたのかな。『幸福の再来』っていう花言葉でしょ。僕はアレクセイと一緒に暮らせるだけで幸福だけ
ど、この子がやって来てもっと幸福にしてくれたんだ」
(あなたの両親の愛の花が僕たちに受け継がれ、この子にも受け継いで欲しいよね)と心の中で付け加える。
アレクセイは思わずユリウスを抱く手に力をこめ、口付けを落とす。
心の中に封じ込めた不滅の恋人が、妻となり、そして間もなく母となる。
ユリウスの足元に散らばるすずらんを拾い上げながら
(おまえはこのすずらんと同じようにロシアの大地に根付いたんだな)
と心の中で思うアレクセイだった。
俺たちの子が生まれたら、俺はこのロシアの大地に咲く野の花をおまえと子供に贈ろう。
厳しいロシアの大地で芽吹き、花咲く名も知れない花かもしれないが、すずらんと同じように俺たち家族の幸福の立会花となって
くれるだろう。
そして、立会花が増えていく度に俺たち家族の歴史も刻まれていくことだろう。
Ende
あとがき 「立会花に寄せて」のオリジナルは2009年にあるサイトに投稿したものです。「すずらんの系譜」はこの話の前日談として書いた
もので、連作として読んで頂きたいと思い、この話の一部を書き換え、加筆し、タイトルも若干変更しました。「すずらんの系譜」
と併せて読んで頂ければ幸いです。

