作:亜琉野(arno)様
「ユリウス様、何か良いことがおありになりましたか?」
ここ半月ばかりふさぎがちで沈んだ表情をしていることが多かったユリウスが、今朝はその美しい青い瞳をキラ
キラさせて溢れるばかりの微笑みを浮かべている姿を見てオークネフは思わず声を掛けた。
オークネフがユリウスの美しい笑顔から視線を手元に移すと、今朝摘んだばかりのすずらんの花束を眼にする。
オークネフの視線がすずらんに注がれたことを感じたユリウスはミハイロフ邸の裏庭ですずらんを見つけた喜び
を自分の胸だけに収めることが出来ず、その喜びをオークネフに伝えたいと思った矢先にオークネフの言葉が発
せられた。
「そのすずらんが咲いている場所は、マクシムがお連れしたのですか?」
ユリウスはオークネフが何故そのことを知っているのか不思議に思いながら深く頷いた。
「そうですか。ユリウス様にあの場所を教えることが出来てマクシムはとても喜んでいるはずです」
マクシムはアレクセイが10才の時に拾ってきたビーグル犬であった。
マクシムはさる貴族の家の犬として生まれたが、生まれた時から後ろ足に障害があり片足を引きずるために生後
間もなく捨てられ、びっこのために町の悪童たちに痛めつけられているところをアレクセイが助け、家に連れ帰
り手当をし育てたアレクセイにしかなつかない犬であった。
それが、ユリウスがミハイロフ邸に来るなりユリウスにすり寄り、片足を引きずりながらいつもユリウスの後を
ついて歩くようになった。
ユリウスにしてもアレクセイのいない淋しさを紛らわしてくれるマクシムは、マルコーと共に大切な存在であった。
「あの場所は私がアレクセイぼっちゃまに教えたのです。毎年すずらんが咲いている時にぼっちゃまはあの場所
で過ごすのが日課で、マクシムが来てからは毎年マクシムと一緒に行っていました。アレクセイばっちゃまがい
なくなってからは、あそこに行けば坊ちゃまに会えると思っているのでしょうか、毎年行くようになっていまし
た。ですから、今年はユリウス様を絶対あの場所に連れて行くと思っていました」
すずらんは「愛している」となかなか口にしないアレクセイの愛の証しであると思っているユリウスは、アレク
セイに聞いても答えてくれないアレクセイのすずらんに込める想いが聞けることを期待してオークネフに問いか
ける。
「アレクセイにとってすずらんはどんな花なの?」
「お聞きではないのですか?ユリウス様にすずらんを贈られたのですよね」
「結婚の時にアレクセイがすずらんの花束を贈ってくれて、すずらんが僕たちの結婚の立会花だったの。それか
らは毎年結婚記念日にすずらんの花束を贈ってくれているけど...でも、聞いてもすずらんのことは詳しくは
教えてくれない」
「すずらんはアレクセイぼっちゃまの御両親の愛の証しなのです。ぼっちゃまの母親であるマリアは捨て子で修
道院で育ったのです。大奥様は寛大な方で、そういう生い立ちの子の数人を修道院から引き取り、邸の小間使い
や下男として雇いました。マリアもその一人で、お母様を亡くされたドミートリィぼっちゃまの小間使いとして
働き始めました。その頃愛する奥様を亡くされたミハイル様は悲しみを忘れるために仕事に没頭し過労のために
倒れられたのです。何人もの高名な医師に診せても病状がなかなか回復しなかったのが、マリアが摘んだ薬草を
煎じて飲ませ献身的に看病するとみるみると快方に向かいました。そして身分を超えた真実の愛が二人の間に芽
生えました。すずらんはマリアが薬草と共に摘んで、ミハイル様の枕元にいつも飾っていた花で、ミハイル様に
とってはすずらんは可憐で健気でまさにマリアそのものでした。すずらんはお二人を結びつけ、お二人の愛を育
んだのです。ドミートリィぼっちゃまもマリアによくなついて、ミハイル様とマリアの間ではしゃぐドミートリ
ィぼっちゃまのお姿は幸福な家族の肖像でした。マリアは修道院で一通りの教育を受けていたので読み書きも出
来ましたし、歌もうまく、清楚で何より気立ての良い娘で、大奥様も気に入りとても可愛がっていましたが、良
家の子女との再婚を強く望んでいたのでミハイル様とのことを認めるはずもなく、怒りのあまりマリアを裏切り
者と呼んだほどです。マリアは大奥様のお気持ちをくんで何度も身を引こうとしましたが、正式な結婚はできな
くともマリア以外の妻はいないと心を定めたミハイル様の誠実な愛に抗えなかったのです。でも大奥様の怒りは
鎮まらないため、ミハイル様はマリアを領地のトボリスクに連れて行き、そこでアレクセイぼっちゃまがお生ま
れになったのです」
ユリウスにとっては初めて聞くアレクセイの両親の話であった。
「俺たちに過去は必要ない。今とこれからを生きればいいさ」と言ってくれたアレクセイは、自分の過去をあま
り話そうとしなかった。
それは、過去を思い出したくても思い出せず、もどかしく思っていた自分へのおもいやりであることがユリウス
には分かっていたので、アレクセイには深く聞けなかった。
でも、今オークネフがユリウスが知りたかったことを語ってくれている。
ユリウスは眼を輝かせながら、オークネフに話の続きを促した。
「アレクセイぼっちゃまにとって、すずらんは特別な花です。ペテルスブルクにやって来たばかりで淋しい時は、
すずらんを眺めては母親を思い出していました。トボリスクではマリアと一緒にすずらんをよく摘んだそうです。
7歳の誕生日に大奥様から子馬のマルコーを贈られた時は嬉しくて、お礼に自分で摘んだすずらんを大奥様に差し
上
げたのですが、まだ心を上手く開くことの出来なかった大奥様はマリアを思い出させるそのすずらんをお
捨<てになってしまったのです。アレクセイぼっちゃまは深く傷ついて、邸を逃げ出してしまいました。私は方々
を探し回ってやっと見つけたアレクセイぼっちゃまを、あの裏庭の茂みに連れて行ったのです。そこはミハイル
様がマリアのために摘んだすずらんが咲いていた所です。私はぼっちゃまに『大奥様の御機嫌を損ねてしまうの
で摘むことは出来ませんが、ここに来れば思う存分にすずらんを眺められますよ』と諭しました。そこには数株
のすずらんが風にその白い可憐な花を揺らしていました。それを見たぼっちゃまは涙をこらえ切れず『ありがと
う、オークネフ』と言いながら私に抱き着き泣いたのですよ」
今朝訪れたあの場所で佇む幼い日のアレクセイの姿を思い浮かべ、思わず涙がこみ上げてしまうユリウスであった。
オークネフもユリウスの青い瞳に浮かぶ涙を見て、すずらんを贈るべき伴侶を得たアレクセイのことを思い、感
無量となるのであった。
ユリウスは涙を拭いながら、笑みを浮かべオークネフに問いかける。
「ねえ、オークネフ。あのすずらんを摘んで自分の部屋に飾ったらおばあ様は今でもお怒りになるかな?」
今朝あの茂みのすずらんを見て、数日後に迫ったアレクセイとの五回目の結婚記念日に自分で摘んで部屋に飾り
たいと思ったのだ。今の騒然としたペテルスブルクの情勢では、今年はアレクセイからの花束を諦めるしかない
と思うと自然に気持ちがふさいでしまうユリウスであったが、今朝のすずらんの発見によりそんな不安が一掃さ
れてしまい、たとえアレクセイが会いに来れなくとも自らの手ですずらんを、それもアレクセイの両親所縁のす
ずらんを摘んで飾れると思うと心が浮き立つのであった。
「いいえ、今の大奥様は昔とは変わられました。ユリウス様と生まれてくるお子さんのためには出来得ることを
して下さいますよ」
「そうだね。おばあ様は本当の孫娘のように僕を慈しんでくれているものね」
オークネフの答えに安堵しながら、お腹に手を当てながらまだ見ぬ我が子に心の中で語りかける。
「君が女の子であったなら愛する男性からすずらんを贈られる女性になって欲しい。男の子だったら愛する女性
にすずらんを贈る男性になって欲しい」
アレクセイの両親から僕たちへ、僕たちから君と君のパートナーへと、すずらんに込める愛が途絶えることなく
受け継がれていくことを強く願うユリウスであった。
Ende
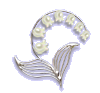 「すずらんの系譜」
「すずらんの系譜」
