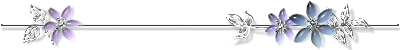
アレクセイが生まれてから住んできた邸がいよいよ閉められ、執事のマヨロフ初め父がペテルスブルクから連れて
きた使用人たちが出発する日がやってきた。
マヨロフと彼の妻で女中頭のオルガ、小間使いのニーナが玄関の前に並び、アレクセイと別れの挨拶をする。
亡くなった女主人のマリア・ユロフスカヤは彼らから見ても慈愛に満ちあふれた聖母であった。
いつも笑顔を絶やさず、声を荒げることもなく、分け隔てもせず、邸の中には常に穏やかな時が流れ、彼らにとっ
てはとても働き易い場所であり、例え出自がどうあろうとも敬愛せずにはいられない存在であった。
毎月の生活も贅沢を控えて質素に努め、仕送りの残金は貧しい者たちや公共の場にまわしていた。
当主のミハイロフ侯爵はペテルスブルクでの仕事が忙しく、年に2、3回しかトボリスクにやって来れなかったが、
妻と息子を深く愛していた。
アレクセイが7歳になるまでにはペテルスブルクに二人を呼び寄せたいと、こじんまりとした邸を手に入れており、
そこで気の置けない友人たちを招いて、マリアと共にサロンを開きたいと思っていた。
正式な結婚に反対した母のことを考えると社交界デビューは控えねばならないが、マリアは素晴らしい妻であり、
日陰の身のままで終わらせたくはなかった。
トボリスクに送り出してから、マリアに貴婦人としての教養を身に着けさせるために家庭教師を付けると、呑み込
みが驚くほど早くどこに出しても恥ずかしくないほどの淑女ぶりであった。
育った修道院で読み書きや歌を習っていたとはいえ、この上達ぶりには高貴な血筋の影響ではないかと思われ秘か
に調査をしていたが、その結果を知る前に侯爵は過労のために再び倒れ、帰らぬ人となったのである。
夫の死はマリアにとって自身の半身を失う以上の打撃であったが、幼いアレクセイのために気力を振り絞り明るく
努める姿が健気であり痛々しくもあった。
しかし、運命はアレクセイに冷酷であった。
父の死後一年も経たないうちに母も病魔に侵され、父の後を追ってしまったのである。
さすがのアレクセイも、自分が生まれる前からこの邸に勤めていて自分のことを何から何まで知っていて慈しんで
くれたマヨロフたちとの別れは胸に迫るものがある。
本来なら彼らは侯爵がペテルスブルクに用意した邸にマリア親子と共に呼び寄せられるはずであったが、夫妻が他
界したために侯爵の母であるヴァシリーサがその邸を処分してしまい、使用人たちも新しい持ち主に雇われること
となったのである。
「いいですか、アレクセイぼっちゃま。きっとペテルスブルクから迎えが来ますからそれまで辛抱なさってくださ
い。折を見てオークネフ様に頼んでみますので、しばらくお待ちになってくださいね」
マヨロフは念を押すようにアレクセイに諭した。
彼はトボリスクに来る前にオークネフの下で働いていたので、アレクセイの両親の事情もよく分かっていたし、侯
爵が遺言で万が一マリアに何かあればペテルスブルクでのアレクセイの教育をヴァシリーサに託していたことも知
っていたのだ。
しかし、アレクセイはペテルスブルク行きには関心がなかった。
自然豊かなトボリスクはアレクセイにとっては格好の遊び場であり、マクシム初め沢山の友達がいるし、何より最
愛の母との思い出に溢れたこの土地を離れたくはなかった。
それに、親友のマクシムの具合が悪いのに自分がいなくなったらマクシムは嘆き悲しむだろうし、また仲間外れに
されてしまうかもしれないという心配もあった。
アレクセイとマヨロフとの間にオルガが分け入ってアレクセイの腕をとり馬車の陰に連れて行った。
そして、声をひそめて話し出した。
「ぼっちゃま。マーサにはお気を付け下さい。奥様の前では大人しくしていましたが、本当はずるがしこい面があ
りますから私は心配でなりません。他の現地雇いの者たちは子沢山や病人がいるために、ぼっちゃまのお世話でき
るのがマーサしかいなかったのが気懸かりです」
「大丈夫だよ、オルガ」と答えたものの、以前から子供心にマーサには余り良い印象を持っていなかったのでオル
ガの不安が的中しそうで少し怖くなった。
「アレクセイぼっちゃま、お身体を大切になさってください。あまり無茶をしないでくださいね」
小間使いのニーナは優しくアレクセイを抱擁する。
「では、ぼっちゃま。お元気で!」
「マヨロフ、オルガ、ニーナ、元気でね!また、いつか会おうね!!」
三人の乗った馬車が走り出し、アレクセイは追い付けなくなるまで全力で後を追った。
やがて、馬車は離れていき、丘の向こうへと消えてしまった。
その姿が見えなくなっても、アレクセイはしばらくその場所に佇んでいた。
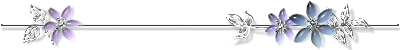
料理女のマーサにひきとられてから、アレクセイの生活は一変した。
養育費目当てでひきとったアレクセイにろくな食事も与えなかった上に、水汲みや薪拾いなどにこき使ったのであ
る。
アレクセイは今までのように自由気ままに野山を駆け巡ることも、友達と遊ぶことも出来なくなっていた。
マーサのこの扱いに周りの者たちは心を痛めたが、近くの町から見回りにやって来る代理人には袖の下を払い、2
ヶ月ごとに養育費を届けに来る弁護士にはうまく取り繕っていたためにどうすることも出来なかった。
「アレクセイ、今日も来なかった!!」
ベッドの中でスケッチ帳をめくりながら、マクシムは残念そうにつぶやいた。
見に来てくれると約束したのに、描いた絵のほとんどをアレクセイは見ていなかった。
息子の肩を落とした姿を見た母親のリーザは諭すように言った。
「仕方ないのよ、マクシム。アレクセイぼっちゃまは以前とは違ってここへは滅多に来れなくなってしまわれたの
だから。さあ、温かくしてもう寝なさい」
秋から病状がさらに悪化し、この冬を越すのは難しい程に弱っている我が子を見るたびに胸が締め付けられるリー
ザであった。
一週間後、マクシムはひどい高熱に襲われ、苦しい息遣いの合間に「父さん」、「母さん」、「アレクセイ」とう
わ言を繰り返した。
枕元で見守るしかないイワンは意を決して立ち上がり、「アレクセイぼっちゃまを連れてくる!!」と妻に言い残
して雪の降る中を出掛けて行った。
苦しむマクシムの姿を眼にしたアレクセイは耐え切れず、「マーサに頼んで医者を呼んでもらう」と叫んで出て行
こうとするのをイワンが制する。
「おやめください!!これがマクシムの寿命だったら受け入れるしかないんです!」
「でも、でも、僕はあきらめたくはないんだ!!」
アレクセイは飛び出して行ってしまった。
雪に足を取られながらアレクセイは考えた。
マーサが医者を呼んではくれないことは頭では分かっている。
しかし、あのまま何もせずマクシムが死んでいくのを黙ってみることはしたくはなかった。
運命を変えられないかもしれないが、この胸に湧き上がってくる怒りのようなものに立ち向かいたかったのである。
マーサに食って掛かって頼んでも医者を呼んではもらえず、罰として食事抜きで部屋に閉じ込められ、仕事以外の
外出を禁じられた。
その夜、一つの小さな命が消えた。
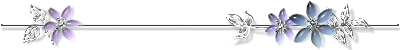
春の息吹がやっと感じられるようになった3月下旬の晴れた日の朝、閉められた邸の前に人だかりが出来ている。
ペテルスブルクへ向かうアレクセイを見送るために、村の大人たちや子供たちが集まっているのである。
マヨロフの働きかけを受けたオークネフが祖母に再三進言して、気に掛かってはいたがなかなか行動に移せないヴ
ァシリーサの背中を押した形で実現したペテルスブルク行きであった。
群衆の中にマクシムの両親もいた。
アレクセイが彼らに会うのは、あの雪の日以来であった。
イワンとリーザが一人一人と別れの挨拶をしているアレクセイに歩み寄ると、イワンが息子の残したスケッチ帳と
パステルの箱を差し出した。
「マクシムが約束して描いた絵です。お見せすることをとても楽しみにしていました。どうか息子の形見として持
っていて下さい!」
スケッチ帳を受け取り中を開くと、マクシムや友達とよく遊んだ森や魚釣りをした川、そしてマクシムとの二人だ
けの秘密の場所が描かれていた。
アレクセイの手がスケッチ帳の最後のページで止まると、小刻みに震えだした。
それを見たイワンとリーザは涙を流しながら言った。
「それはマクシムが描いた最後の絵です。『今年もアレクセイと一緒にすずらんを摘みに行けないから、お詫びに
この絵を描いたんだ』と言っていました」
その絵は一昨年母とマクシムと三人ですずらんを摘みに行ったあの丘の絵で、すずらんを手にしたマリアの回りを
アレクセイとマクシムがはしゃぎながら走っている場面であった。
(ありがとう、マクシム。この絵を見ればいつでもママとマクシムに会えるね。あの丘もすずらんも一年中見るこ
とができるんだね)
アレクセイは鳶色の瞳にうっすらと涙を浮かべながら感謝し、スケッチ帳を胸に抱きしめた。
この中に僕のトボリスクの思い出がすべて詰まっているんだと思いながら、イワンとリーザにお礼を言おうとする
と、リーザがこらえきれず泣き崩れ、イワンがしっかりとその肩を抱いた。
(そうだ、イワンとリーザにとってもこれは掛け替えのないマクシムの形見なのだ。僕が一人占めすることはでき
ない!!)
アレクセイはスケッチ帳から最後のページを切り取り、スケッチ帳をイワンに返した。
「僕はこの絵とパパからもらったパステルがあればいいから、スケッチ帳は二人に持っていて欲しいんだ」
「有難うございます!!アレクセイぼっちゃま!!」
リーザの涙はうれし涙へと変わっていく。
迎えに来た弁護士のオブローモフが「さあ、ぼっちゃま。そろそろ出発しましょう」と促す。
アレクセイは馬車に乗り込み、窓から身を乗り出して集まってくれた村人たちに最後の別れをする。
馬車が走り出すと大人たちは大きく手を振り、子供たちは村はずれまで走ってついてくる。
彼らに手を振り続けていたアレクセイは子供たちの姿が見えなくなってから座席につき、マクシムの絵を膝の上に
のせて窓から景色をながめていると、右手にあのすずらんの丘が見えてくる。
(もうママのお墓にすずらんを持っていくことは出来ないから、ペテルスブルクですずらんを見つけてこの絵の前
に飾るから許してね。でも、ママのお墓からあの丘もふもとに咲くすずらんも見えるから僕はちょっと安心なんだ)
丘に向かって語りかける。
母の立場と出自から考えて自分は祖母には歓迎されないことをうすうす勘付いているアレクセイであったが、異母
兄のドミートリィーに会えるという唯一の楽しみには胸が躍っていた。
母からは折に触れてドミートリィーの素晴らしさを知らされていたし、父が来る度に「ドミートリィーは弟のアレ
クセイにいつも会いたがっているんだよ」と聞かされていたので、「いつか会ってみたい!!」とずっと思ってい
たのである。
馬車はアレクセイの不安と期待ものせて進んで行く。
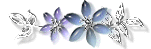 Ende
Ende

 「トボリスクの思い出」
「トボリスクの思い出」
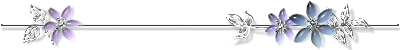
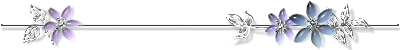
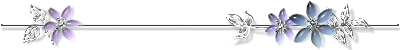
Ende
